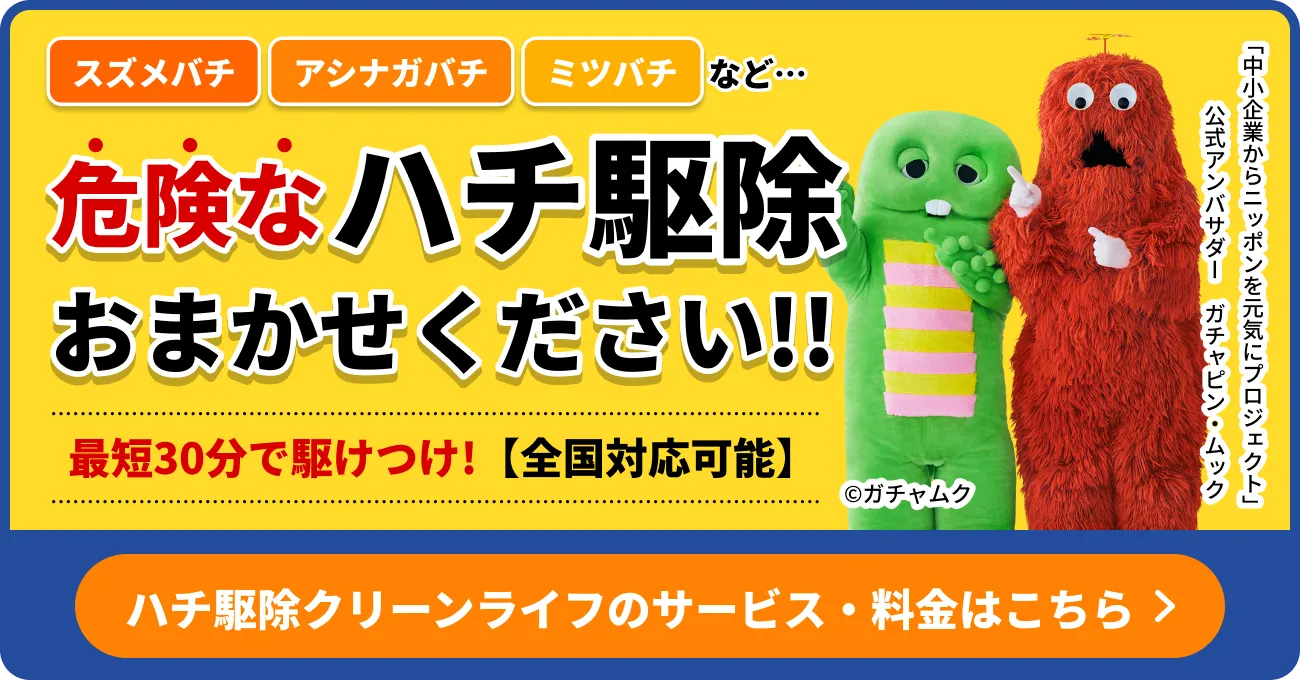- トップ
- クロスズメバチの生態や危険性を徹底解説!正しい対処法も紹介

クロスズメバチの生態や危険性を徹底解説!正しい対処法も紹介
本記事では、クロスズメバチの特徴・生態・危険性・対処法・駆除方法を解説していきます。
クロスズメバチは、体は小さめで一見するとそれほど危険には思えませんが、実は巣を刺激すると集団で襲ってくる攻撃性を持っており、うっかり踏んでしまって刺される事故も多い厄介な存在です。
日本全国に広く分布し、住宅の近くでも見かけることのある身近なハチなので、ぜひ正しい知識と対処法をご確認ください。
Contents
クロスズメバチの特徴

クロスズメバチは、その名のとおりスズメバチの仲間ではありますが、見た目や性格、巣の作り方などがほかのスズメバチとは少し異なります。
体はとても小さく、蜂に詳しくない人からするとブヨやハエと見間違えることもあるほどの大きさです。
しかし、小さいからといって巣に近づいたり踏みつけたりすると、集団で襲ってくることもあるので油断は禁物です。
ここでは、クロスズメバチの見た目・サイズ・分布エリア・活動時期など、基本的な特徴を詳しく紹介していきます。
体長10mm前後と小さい
クロスズメバチは、体長がわずか10mm前後と非常に小型のスズメバチです。
これは一般的なスズメバチの半分以下のサイズで、遠目にはアブやブヨ、ハエと間違われることも良くあります。
見た目が控えめなことから、危険性が低いと思われがちですが、実は巣を刺激されると集団で襲いかかってくるという性質を持っており、決して油断はできません。
小さいぶん、飛行音も静かで気づきにくいため、近くにいても存在に気づかないことがあります。
庭先や畑で作業していて突然刺された…というケースも多く報告されており、“見た目より警戒すべき存在”だと言えるでしょう。
黒色と白色の模様が特徴
クロスズメバチの体色は、黒と白色のしま模様が特徴的です。
全体的につやのない黒色をしており、控えめに細い白ラインが数本は言っています。
また足は先まで白いのもポイントです。
体が小さいため、近くでじっくり観察しないとわかりにくいかもしれません。
この模様は、アブやハナアブなどの無害な昆虫とも似ていますが、見慣れてくると、クロスズメバチ特有の丸みを帯びたコンパクトな体と、やや地味な色味の縞模様で判別できるようになります。
見た目の似た昆虫が多い中で、しっかり識別できる知識を持つことが、刺傷事故を避けるための第一歩です。
ブヨと見た目が似ている
クロスズメバチは体が小さく、羽音も控えめなため、前述の通り「ブヨ」や「アブ」と間違えられやすいハチです。
特に黒っぽい体色やサイズ感がブヨに似ており、刺されてから初めて「実はハチだった」と気づく人も少なくありません。
見分けるポイントとして、ブヨはまっすぐにしか飛べないのに対し、クロスズメバチは空中でホバリング(停止飛行)できるという大きな違いがあります。
飛び方に注目することで、誤認を防ぐ手がかりになるでしょう。
また、ブヨは皮膚をかじって吸血するのに対し、クロスズメバチは毒針で刺して攻撃してくるため、刺された直後の痛みが鋭く、腫れや炎症も強く出やすいのが特徴です。
小さな虫だからと油断せず、行動パターンや飛び方を観察する習慣が大切です。
日本全国に広く生息している
クロスズメバチは、北海道から沖縄まで日本全国に広く分布しているスズメバチです。
基本的に山間部や森林に巣を作りますが、都市部の公園・民家の庭・畑・空き地など、人が暮らすエリアにも生息しているため、誰にとっても無関係ではない存在です。
適応力が高く、都市部のちょっとした植え込みや建物のすき間などにも巣を作ることがあり、「こんなところに!?」と驚くケースも少なくありません。
また、土の中に巣を作る習性があるため、気づかずに踏んでしまって刺される事故も多いです。
全国どこでも遭遇の可能性があるからこそ、あらかじめ知識を備えておくことが大切です。
春から12月頃まで活動する
クロスズメバチの活動期間は、春(4月頃)から冬の始まり(12月頃)までと、かなり長いのが特徴です。
初春には女王バチが冬眠から目覚めて巣作りを開始し、夏〜秋にかけて働きバチの数が増加、そして晩秋から冬の入り口まで活動を続けるケースも多く報告されています。
とくに夏の終わりから秋にかけては注意が必要です。
この時期は巣の規模が最大化し、防衛本能も強くなるため、ちょっとした刺激でも集団で攻撃してくる可能性が高まります。
また、他のスズメバチが活動を終えていく11月頃でも、クロスズメバチはまだ動いていることがあるため、「もう寒いから虫もいないだろう」と油断していたら刺された、なんてことも。
活動期間が長い分、注意するシーズンも長くなると覚えておきましょう。
クロスズメバチの生態

クロスズメバチは、巣の作り方、働きバチの数、食性、そして繁殖のサイクルなど、他のスズメバチとは異なる特徴がいくつもあります。
クロスズメバチの生態を把握することで、遭遇リスクや被害防止のヒントになる情報を詳しく解説していきます。
土中に小さな巣を作る
クロスズメバチの最大の特徴のひとつが、地面の中に巣を作るという点です。
古い木の根元や芝生の下、植木鉢の下など、人の目につかない土の中やその近くに小さな球状の巣を作ることが多く、発見しにくく大きさも分からないのが厄介なポイントです。
巣の入り口は小さな穴だけで、見た目にはまるで虫の巣穴や雨水の跡のように見えることも。
そのため、知らずに踏んでしまい、突然刺されるという事故が多発しています。
草むら・畑・庭先で、急にクロスズメバチの姿が消えた場合は近くに巣穴があるかもしれないので足元のチェックを忘れずに行いましょう。
ピーク時は 1000~3000頭と大所帯になる
クロスズメバチは初期段階では数十匹程度の小さな群れですが、夏の終わりから秋にかけて活動がピークを迎えると、一つの巣に1000〜3000頭もの個体が存在する大所帯に成長することがあります。
見た目は小さな穴でも、その地下には巨大な巣が広がっているケースもあるため、油断は禁物です。
この時期のクロスズメバチは巣を守る意識が非常に強く、少しの振動や刺激でも集団で襲いかかってくる危険があります。
巣の規模は掘り起こしてみないと分からないため、自力駆除ではなく専門業者に相談する判断が重要です。
雑食性で花の蜜や昆虫を食べる
クロスズメバチは、非常に幅広い食性を持つ雑食性のハチです。
主なエサは花の蜜や果実などの糖分ですが、他にもアブラムシ・小さな昆虫・クモなども捕食するため、肉食性の一面も持っています。
ジュースやお菓子の香りにも惹かれて寄ってくるため、屋外での食事中に不意に近づかれることもあるのでキャンプなどでは特にご注意ください。
また、幼虫には肉食性の餌を与え、大人(成虫)は糖分を摂るという親子で異なる食生活をしている点も特徴的です。
女王蜂は冬を越し春に巣を作り始める
クロスズメバチは、冬になると女王バチだけが越冬します。
そして、春が訪れると活動を再開し、単独で小さな巣を作り始め、卵を産んで最初の働きバチを育てていきます。
春の時期は巣の規模がまだ小さく、働きバチも少ないため、駆除を検討するには最も適したタイミングです。
反対に、この時期に見逃してしまうと、夏から秋にかけて巣がどんどん大きくなり、危険度も増していきます。
なお、越冬中の女王バチは物陰や壁のすき間に潜んでいることがあります。
女王バチに刺されるケースも少なくないので冬だからと言って油断は禁物です。
クロスズメバチの危険性

クロスズメバチは体が小さく、他のスズメバチに比べて目立たない存在ですが、危険性が無いわけではありません。
巣が土の中などに隠れているため、人が気づかず踏んでしまい、突然刺されるケースが後を絶ちません。
ここでは、クロスズメバチの具体的な危険性について、事例を交えながら解説していきます。
気づかず巣を踏んで刺されることが多い
クロスズメバチの巣は、地面の中や草むらの中など、非常に見つけにくい場所に作られることが多く、気づかずにその上を通ってしまうことがよくあります。
特に庭や畑、空き地、キャンプ場などでは、うっかり巣を踏んでしまうケースが後を絶ちません。
屋外での作業やレジャーでは、足元に注意を払い、小さな穴や虫の出入りが見える場所には近づかないことが大切です。
巣を刺激すると集団で襲ってくる
クロスズメバチは、普段は人に対して積極的に攻撃してくるタイプではありません。
しかし、巣を刺激されたと判断すると、一気に防衛モードに切り替わります。
一匹が威嚇行動を始めると、巣の中から複数の働きバチが次々と飛び出し、集団で襲いかかってくるという非常に危険な状況になることもあります。
また、土の中にある巣の大きさがわかりにくく、大規模な巣を刺激してしまった場合は大量のハチに襲われる危険があり大変危険です。
クロスズメバチをよく見かける地域で草刈りなどを行う場合は慎重に行動することが何より重要です。
刺されると激しい痛みと腫れが発生する
クロスズメバチは体こそ小さいものの、毒針による攻撃力は決して侮れません。
毒の量は少ないですが、刺された瞬間には鋭い痛みが走り、その後、刺された部位が赤く腫れて熱を持つことが一般的です。
場合によっては、数日間にわたって腫れが引かないこともあります。
さらに、ハチ毒に対するアレルギー反応(アナフィラキシー)を持つ人は、命に関わるような重篤な症状を引き起こす恐れもあるため、過去にハチに刺された経験がある方は特に注意が必要です。
刺された際には、すぐに患部を流水で洗い流し、冷やしてから様子を見ることが基本ですが、腫れや痛みが強い場合や体調に異変を感じた場合は、ためらわず医療機関を受診しましょう。
クロスズメバチを発見した時の対処法

クロスズメバチを見かけたとき、どう行動すべきかを知っているかどうかで、被害のリスクは大きく変わってきます。
ここでは、クロスズメバチを発見したときの基本的な注意点から、生活圏内に巣がある場合の対応方法までをわかりやすく解説します。
落ち着いて行動するために、ぜひ事前に把握しておきましょう。
むやみに近づかない
クロスズメバチを見かけた場合、まず何よりも大切なのは「近づかない」ことです。
体が小さいため、つい軽視してしまいがちですが、攻撃性はしっかり備えており、巣を刺激されれば必ず攻撃されます。
警戒フェロモンで仲間を呼び寄せる習性があるため、1匹に攻撃されたことをきっかけに、複数匹に囲まれてしまうこともあるので、手で払ったりせず静かに距離を取るのが鉄則です。
甘い香りや黒いものに寄ってくるので注意する
クロスズメバチは、花の蜜や果実を好むことから、甘い香りに強く引き寄せられる習性があります。
ジュース・アイス・お菓子・果物などを屋外で食べていると、気づかないうちに近寄ってくることがあるため、特に夏場の屋外レジャーやバーベキューでは注意が必要です。
また、黒い服や帽子なども、攻撃対象として認識されやすいことがわかっています。
これは黒いものを「敵」とみなす習性があるためで、特に頭部などの露出が多い部分が狙われやすくなります。
屋外での活動時には、白っぽい服を着る・甘い香りの化粧品や整髪料を避ける・飲食物を放置しないなど、ちょっとした工夫で被害のリスクを下げることができます。
生活圏内に巣がある場合は早めに駆除する
クロスズメバチの巣が、自宅の庭・玄関付近・通路沿いなど、人の生活圏内にある場合は、できるだけ早めの対応が重要です。
特に、地面や壁のすき間にひっそりと作られた巣は発見が遅れがちで、気づいた頃には働きバチが増えて危険度が上がっていることもあります。
子どもやペットがいる家庭では、うっかり巣に近づいたり踏みつけたりするリスクも高いため、早期の判断がカギになります。
巣がまだ小さいうちであれば、自力での駆除が可能な場合もありますが、場所や規模によっては専門業者に相談するのが安全確実な選択肢です。
クロスズメバチを駆除するには

クロスズメバチの巣を見つけたとき、「自分で駆除できるのか?」「業者に依頼すべきか?」と迷う方も多いと思います。
実は、巣の大きさや場所、活動時期などによって最適な対処法が変わってきます。
ここでは、駆除のタイミングや方法、自力で対応できるケースと業者に依頼した方がよいケースの見極めポイントを解説していきます。
安全第一で、状況に合った方法を選びましょう。
初期の巣なら自力で駆除できる
クロスズメバチの女王バチが単独で巣を作っている初期段階(春〜初夏)であれば、自力での駆除も十分可能です。
巣の大きさがピンポン玉〜テニスボール程度であれば、働きバチの数も少なく、攻撃を受けるリスクが低いためです。
この場合は、防護服や長袖・長ズボンなどを着用し、市販のスズメバチ用スプレーを使って駆除するのが基本的な方法です。
作業後はすぐにその場を離れ、しばらく様子を見てから巣を撤去するようにしましょう。
巣が地中にあるため駆除が難しい
クロスズメバチは、地面の中や物陰に巣を作ることが多いため、発見しづらく、駆除の難易度も高いという特徴があります。
しかも入り口は小さくても、その下に大規模な巣が広がっているケースもあるため、油断は禁物です。
市販スプレーを使っても薬剤が巣の奥まで届かず、かえってハチを刺激して逆襲を受ける可能性があるため、初期段階を過ぎた時期の駆除はプロの業者に相談することをおすすめします。
専門業者に依頼が確実
もう、巣が大きくなっている時期・働きバチが多数いる・場所が危険という場合は、迷わず専門の蜂駆除業者に依頼しましょう。
プロであれば専用の防護服や器具を使い、安全に迅速な駆除が可能です。
また、巣の再発防止処置や周辺環境の点検なども任せられるため、結果的に安心・確実・効率的です。
駆除にかかる費用は業者によって異なりますが、被害やリスクを考えれば、十分納得のいく選択と言えるでしょう。
クロスズメバチの駆除ならハチ駆除専門クリーンライフへ相談!

クロスズメバチは体こそ小さいものの、地中に潜む巣・突然の集団攻撃・見落としやすい生息場所など、非常に厄介な一面を持っています。
特に夏〜秋にかけて巣の規模が大きくなると、被害リスクは一気に上昇しますので自力での駆除は困難を極めます。
そんなとき頼れるのが、蜂駆除のプロフェッショナル「クリーンライフ」です。
経験豊富なスタッフによる対応で、安全・迅速・的確に駆除が可能です。
見積りも無料なので「ちょっと相談してみたい」「この巣、放っておいて大丈夫?」という段階でも気軽にご連絡いただけます。
危険ですので、無理せず
まずはプロに相談を!
- お支払い方法
-
- 現金払い

- 各種クレジットカード対応

- コンビニ後払い

- 銀行振込

- QR決済