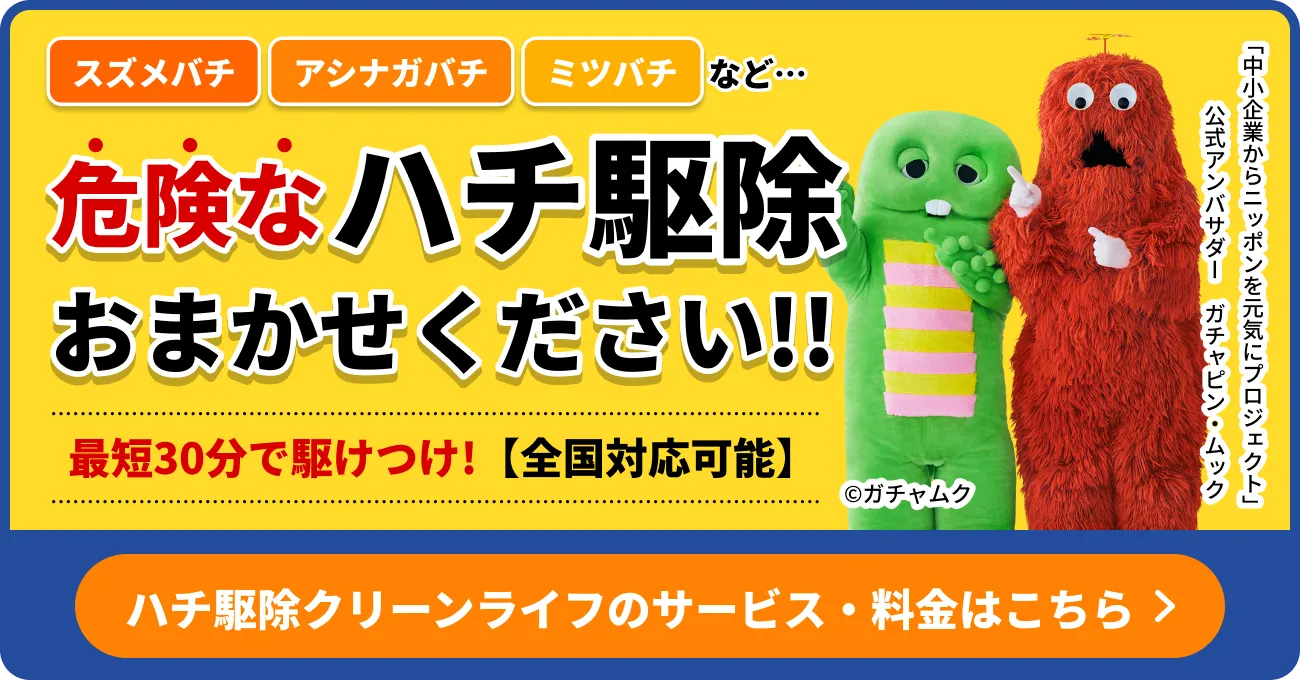- トップ
- 危険性は低くても油断は禁物なヒメスズメバチについて徹底解説

危険性は低くても油断は禁物なヒメスズメバチについて徹底解説
ヒメスズメバチの特徴や生態、危険性から巣の対処法、駆除方法までを徹底解説します。
ヒメスズメバチという名前からかわいらしいイメージが沸くかもしれませんが、実は体の大きさは国内でもトップクラスのスズメバチです。
基本的にはおとなしいハチですが、秋になると攻撃性が増すため、注意が必要な存在であることに変わりはありません。
安心・安全な暮らしのために、しっかりと知識を身につけておきましょう。
Contents
ヒメスズメバチの特徴

ヒメスズメバチの体は非常に大きく、一見すると凶暴そうに見えるものの、実は比較的温厚な性格をしています。
見た目と実際の性質にギャップがあるため、正しく理解しておかないと過剰に恐れてしまったり、逆に油断してしまったりする可能性があります。
この章では、ヒメスズメバチの外見や性格、生態的な特性について詳しくご紹介していきます。
国内トップクラスで大きい
ヒメスズメバチは、体長が働きバチで約25〜30mm、女王バチでは35mmを超えることもあるほど、日本国内でも最大級のサイズを誇ります。
特にその大きさから、初めて目にした人は危険なオオスズメバチと勘違いすることもあるほどです。
羽音も非常に大きく、近くを飛ばれるだけで恐怖を感じる人も少なくありません。
とはいえ、外見の迫力とは裏腹に比較的おとなしい性格のため、むやみに刺激しなければ攻撃してくることはほとんどありません。
見た目に惑わされず、正しい知識で冷静に対処することが大切です。
お尻の先端が黒い
ヒメスズメバチを見分けるポイントのひとつに、腹部の先端(お尻)が黒くなっているという特徴があります。
一般的なスズメバチは、腹部に黄色と黒の縞模様が目立ちますが、ヒメスズメバチはその縞がやや控えめで、特に腹部の末端にかけて黒が濃くなるのが特徴的です。
全体としては濃い茶色〜黒っぽい色合いで、落ち着いた印象を受けることもあります。
この「お尻の黒さ」は、他のスズメバチやアシナガバチとの識別にも役立つポイントです。
巣の近くで見かけたときなど、少し離れた距離からでもこの特徴に気づければ、早めの注意・対策に繋がります。
比較的温厚で益虫でもある
ヒメスズメバチは、スズメバチの中でも比較的おとなしい性格をしており、人間に対して積極的に攻撃してくることは少ないとされています。
巣を刺激したり、近づきすぎたりしない限りは、こちらを無視して通り過ぎていくことがほとんどです。
そのため、他の攻撃的なスズメバチに比べ、必要以上に恐れる必要はありません。
また、ヒメスズメバチは毛虫や小型の昆虫を捕食する習性があり、農作物や庭木を守る「益虫」としての一面も持っています。
過度に駆除してしまうと、生態系バランスに影響が出る可能性もあるため、正しく共存していく姿勢が求められます。
特殊なヒメスズメバチの生態

ヒメスズメバチは、その見た目や性格だけでなく、ほかのスズメバチには見られない独特な生態を持っていることでも知られています。
たとえば、活動時間帯や子育ての方法、季節による行動の変化など、一風変わった特徴が多く見られます。
この章では、ヒメスズメバチならではの行動パターンに注目して詳しく解説していきます。
昼間に活動するが人目につきにくい
ヒメスズメバチは昼行性で日中に活動しますが、人の目に触れにくい場所で静かに暮らすため、気づかないうちに近くに巣を作っていることもあります。
日本のスズメバチ属の中でも最も小型の巣を作り、働きバチの数も少ないため、活動が目立ちにくいのです。
また、ヒメスズメバチは土の中や屋根裏、床下、木のうろ、切り株の内部、壁の隙間など、閉鎖された目につきにくい場所を好んで巣を作る傾向があります。
さらに、冬を越した女王バチの活動開始時期が遅いため、他のスズメバチよりも活動期間が短く、人との接点も限られるのが特徴です。
そのため、「見かけない=いない」と油断しないよう注意が必要です。
アシナガバチの幼虫で子育てする
ヒメスズメバチには、アシナガバチの巣に侵入し、その幼虫を奪って自分の幼虫のエサにするという驚きの子育て方法をします。
巣を乗っ取るわけではありませんが、アシナガバチの巣に女王バチが単独で入り込み、幼虫だけを狙って運び去るのが特徴です。
1匹のヒメスズメバチに巣を襲われたアシナガバチは100匹以上いても反撃することはなく、巣を離れてしまいます。
このような習性は、ヒメスズメバチが生息環境での捕食対象を効率的に見極めて行動していることを示しており、自然界における捕食者としての側面も持っています。
人間をあまり襲うことがないおとなしい性格とは裏腹に、野生ならではのしたたかさを持ったハチだと言えるでしょう。
6月から活動的になる
ヒメスズメバチは毎年6月頃から本格的に活動を始めます。
冬を越した女王バチが春先から巣作りを始め、6月には働きバチが育ち始めて一気に活動が活発化します。
この時期になると、エサを探して飛び回る姿が見られるようになり、住宅周辺や庭先などでも遭遇の可能性が高まります。
ただし、活動の開始が比較的遅めであること、かつ活動期間も他のスズメバチに比べて短いため、ピークは夏の中盤から秋口にかけてとなります。
とはいえ、巣作りが始まる初期段階から警戒しておくことで、被害を未然に防ぐことが可能でしょう。
6月をひとつの目安として、屋根裏や床下、庭の隅などに異常がないかチェックしておくと安心です。
ヒメスズメバチの危険性

ヒメスズメバチは比較的おとなしい性格とされていますが、だからといって決して油断してよい相手ではありません。
とくに巣に刺激を与えた場合や、秋の繁殖期に入ったタイミングでは、攻撃性が一気に高まります。
さらに、毒針の構造は他のスズメバチ同様に強力で、刺されると激しい痛みと長引く腫れに悩まされることもあります。
この章では、見落とされがちな危険ポイントをわかりやすく解説していきます。
巣を刺激されると攻撃的になる
ヒメスズメバチは普段はおとなしく、人間に対して積極的に攻撃してくることは少ないと言われています。
しかし、巣を刺激されたときだけは話が別です。
巣に近づいたり、不用意に物をぶつけてしまったりすると、防衛本能が働いて一気に攻撃モードに入ります。
複数の働きバチが一斉に飛び出してきて、刺してくるケースもあります。
とくに子育ての最盛期である夏場や、女王を守る意識が高まる秋には、より敏感になっているため注意が必要です。
普段がおとなしいからといって軽視せず、巣の存在に気づいたらむやみに近づかず、専門家に相談するのが安全です。
針が太いため強く痛み長く腫れる
ヒメスズメバチの体は大型である分、毒針も太くてしっかりと刺さる構造になっています。
そのため刺されたときの痛みが非常に強く、まるで焼けるような激痛を感じることもあり危険です。
他のスズメバチと比べれば毒性は低めですが、刺されるとアレルギー反応を起こすこともあります。
過去にハチに刺されたことのある人や、アナフィラキシーの経験がある人は特に注意が必要です。
刺されたらすぐに流水で洗い、可能な限り早く病院を受診するようにしてください。
秋は攻撃性が増す
夏の終わりから秋にかけて、ヒメスズメバチの攻撃性は一気に高まります。
その理由は、巣の中で育った新女王バチとオスバチを守るために、働きバチたちが非常に神経質になるからです。
この時期は外敵やわずかな刺激に対しても過敏に反応し、人が近づいただけでも威嚇や攻撃に出るケースが増えます。
普段は温厚なヒメスズメバチであっても、秋だけは別物と考えるべきです。
うっかりヒメスズメバチの巣から5m以内に近づいてしまうと、顎をカチカチと鳴らして警戒音を立てたり、羽音が聞こえるぐらいの近くを飛んだりと威嚇していきます。
この場合は、大きな声を出したり手で振り払ったりせず、ゆっくりとその場を離れるようにしてください。
ヒメスズメバチの巣の特徴と対処法

ヒメスズメバチの巣は、目立ちにくい場所に作られることが多く、気づきにくいのが特徴です。
しかし、もし自宅の敷地内やその周辺で見つけた場合、正しい知識がなければ不安に感じてしまうこともあるでしょう。
この章では、ヒメスズメバチの巣の見た目や場所の傾向、対処すべきケース・放置しても問題ないケースなどを解説します。
無用な駆除やトラブルを防ぐためにも、巣の特徴を正しく理解しておくことが大切です。
閉鎖空間に球状の巣を作る
ヒメスズメバチは、土中・屋根裏・床下・樹木の空洞・壁のすき間など、閉鎖的で暗く静かな場所に好んで巣を作る傾向があります。
巣の形状はシャワーヘッドのような形をしており、捕食しているアシナガバチの巣と似た形状をしています。
下から見ると巣盤の層が見えるような構造になっており、巣が完成すると球状のドーム型になります。
閉鎖空間に巣があることで、人との接点が少ない反面、知らずに近づいたり振動を与えたりしてしまうと、攻撃を受けるリスクも高くなり注意が必要です。
巣の大きさは約10cmと小さめ
ヒメスズメバチの巣は、他のスズメバチに比べて非常にコンパクトです。
多くの場合、直径10cm程度の小さな球状で、巣の中にいる働きバチの数も少なく、全体としてこじんまりとした所帯を築くのが特徴です。
そのため、遠くから見ても目立ちにくく、周囲に草木があれば完全に隠れてしまっていることもあります。
とはいえ、小さいからといって油断は禁物です。
巣を刺激すると一斉に襲ってくる可能性があるのは他のスズメバチと変わりません。
大きさではなく「場所」と「状況」によって危険度が左右されるため、発見した際は落ち着いて対応を判断しましょう。
人通りのない場所なら放置で問題無い
ヒメスズメバチは攻撃性が低く、巣が人目につかない場所にある場合は、無理に駆除しなくても大きな問題にならないことが多いです。
たとえば、裏山の土中や空き地の木の中など、明らかに人が近づかないような場所に巣がある場合は、放置しても危険性は低く、自然の一部として共存するという選択もアリです。
ハチは生態系のバランスを保つ大切な役割を担っている生き物でもあります。
生活に支障がない場所であれば、無理に駆除せず、できるだけそっと見守ってあげるのが理想的です。
私たち人間の安全を守りつつ、ハチの生態を正しく理解して、うまく付き合っていくことが、これからの共存のカタチと言えるでしょう。
ヒメスズメバチを退治する方法
巣の場所や規模、人との距離によっては、ヒメスズメバチを駆除する必要が出てくることもあります。
比較的おとなしいとはいえ、誤って刺激すれば集団で襲ってくる可能性は十分にあるため、駆除を行う際には慎重な判断と準備が欠かせません。
ここでは、夜間の駆除がなぜ効果的なのか、どんな手順で行うべきか、そして最終手段として専門業者に頼むべきタイミングなど、安全かつ確実に駆除するための方法を分かりやすく解説していきます。
成功率が高い夜間に駆除する
ヒメスズメバチを駆除する際は、夜間に行うのが最も安全かつ成功率が高い方法です。
夜になると働きバチたちは活動をやめて巣に戻り、光に対する反応も鈍くなるため、駆除作業中の攻撃リスクが大きく下がります。
なお、作業時には、懐中電灯に赤いセロファンをかぶせて光をやわらげる工夫をしましょう。
ハチは赤い色を認識しにくいため、なるべくソフトな赤い光で照らすのがポイントです。
また、夜間であっても長靴・手袋・防護服などの完全防備は必須です。安全第一で臨んでください。
特に4〜5月の巣はまだ働きバチが少なく、小さな巣には女王バチと幼虫しかいない場合が多いため、この時期を狙えば比較的安全に駆除が可能です。
防護服を着て風上から殺虫スプレーをかける
自力で駆除する場合は、徹底した装備と立ち回りが命を守るカギとなります。
まず、防護服・手袋・長靴・フェイスガードなど全身を覆える装備を用意してください。
ヒメスズメバチの針は太く、通常の服では貫通することもあるため、肌の露出は絶対NGです。
スプレーを使用する際は、必ず風上から行うことが鉄則です。
風下に立ってしまうと、自分に薬剤がかかってしまうので危険です。
また市販のスズメバチ用スプレーは、ピレスロイド成分の入っている噴射距離が5〜7メートルほどあるものが推奨されます。
スプレーは巣に向かって1本まるごと使い切るつもりで噴射しましょう。
業者に依頼する
おとなしいヒメスズメバチとはいっても駆除が必要になった場合は、専門の業者に依頼するのが最も安全で確実な方法です。
とくに7月以降になると働きバチの数が増え、巣の防衛本能も強くなるため、個人での駆除は一気に危険度が高まります。
さらに巣の場所や大きさによっては、刺されるリスクはもちろん、落下や転倒などの事故につながる可能性もあります。
プロの駆除業者であれば、専門の防護服・高所作業のノウハウ・専用薬剤や道具を駆使して、安全に迅速な対応が可能です。
また、周辺の再発防止策や安全な撤去後処理まで行ってくれることが多く、安心感もあります。
少しでも危険を感じたら、迷わず専門業者に相談するのが賢明な判断です。
ヒメスズメバチの駆除は蜂駆除専門クリーンライフにお任せがおすすめ

ヒメスズメバチは一見おとなしい印象を持たれがちですが、時期や状況によっては非常に危険な存在にもなり得ます。
とくに7月以降は巣の規模も大きくなり、働きバチの数も増加するので自力での駆除はリスクが高く、おすすめできません。
そんなときに頼れるのが、蜂駆除専門クリーンライフです。
現地の状況に応じた最適な対応をスピーディに行い、防護・駆除・再発防止策までトータルで対応、さらに、見積もりも無料と気軽に相談できるのも大きな安心ポイントです。
「これって放置しても大丈夫?」「今すぐ何とかしたい!」と感じたら、迷わず蜂駆除専門クリーンライフへご相談ください。
危険ですので、無理せず
まずはプロに相談を!
- お支払い方法
-
- 現金払い

- 各種クレジットカード対応

- コンビニ後払い

- 銀行振込

- QR決済