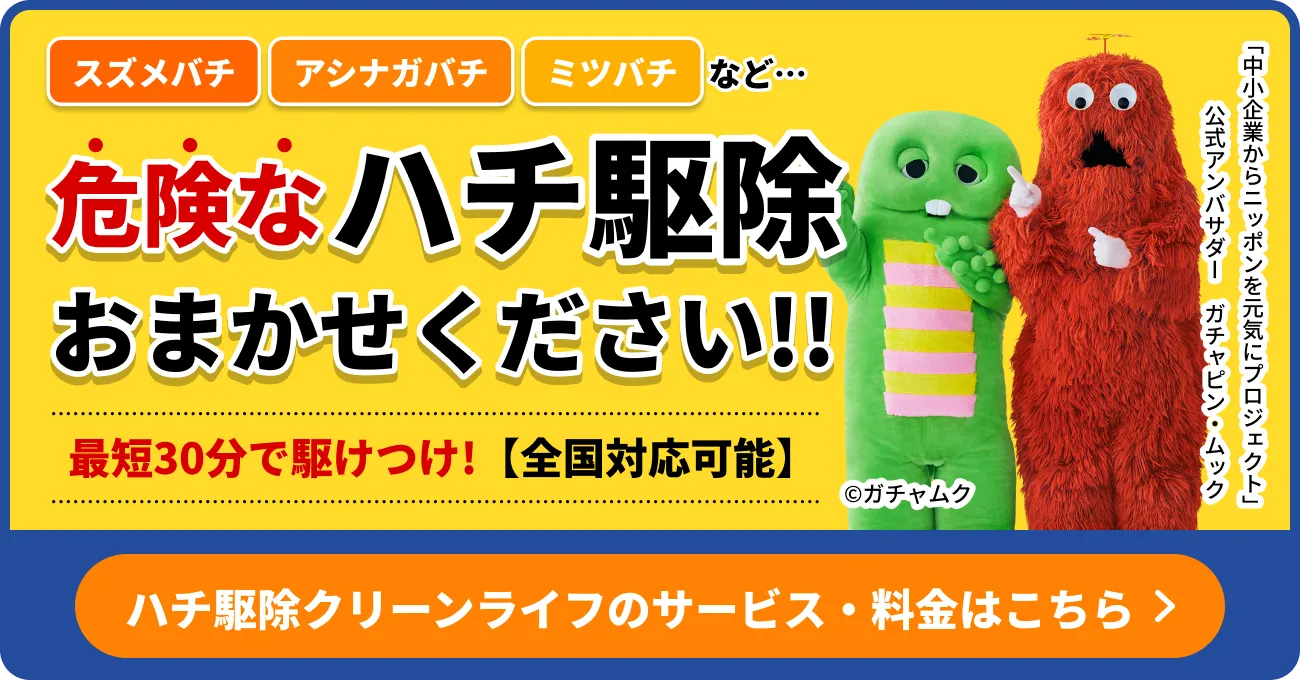- トップ
- 日本に生息するアシナガバチの種類を徹底解説|11種類の特徴や見かけた時の対処法も

日本に生息するアシナガバチの種類を徹底解説|11種類の特徴や見かけた時の対処法も
庭やベランダでよく見かけるアシナガバチ。実は、多くの種類に分かれているのをご存じでしょうか。
本記事では、アシナガバチの種類を詳しく解説します。
アシナガバチは、人間の生活環境のそばに巣を作りやすい性質があります。その分、種類による攻撃性の違いや習性が気になる方も多いはず。
そこで、日本に生息する代表的な種類の特徴や、人への危険性をわかりやすく解説します。アシナガバチを見かけた時の、種類問わず安全な対処法も紹介するので、身近でアシナガバチを発見した時も、落ち着いた行動が取れるようになるでしょう!
Contents
日本に生息するアシナガバチの種類
早速、日本に生息するアシナガバチを11種類、詳しく解説していきます。
一言でアシナガバチと言っても、以下の表の通りに3つの属性に分かれるほど、種類が豊富です。
| 属性 | 種類 |
|---|---|
| アシナガバチ属 | セグロアシナガバチ キアシナガバチ フタモンアシナガバチ トガリフタモンアシナガバチ キボシアシナガバチ コアシナガバチ ヤマトアシナガバチ |
| ホソアシナガバチ属 | ムモンホソアシナガバチ ヒメホソアシナガバチ |
| チビアシナガバチ属 | オキナワチビアシナガバチ ナンヨウチビアシナガバチ |
それぞれの種類ごとに、見ていきましょう。
セグロアシナガバチ|攻撃性が比較的強い

まず、セグロアシナガバチをご紹介します。
| 生息地 | 沖縄~本州北部
平地に多い |
|---|---|
| 活動時期 | 4~11月 |
| 大きさ | 21mm~26mm |
| 特徴 | 体色は黒褐色で胸部に黄色の模様 攻撃性が強く刺される事故が多い 家屋周辺や植木によく巣を作る |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:高い 攻撃性:高い |
セグロアシナガバチは、日本で最もよく見られるアシナガバチの一種で、大きさは、働きバチで約21〜22mmほど。黒っぽい体色に黄色い縞模様が特徴です。
スズメバチより攻撃性は低いとされるアシナガバチですが、セグロアシナガバチは、他のアシナガバチよりも警戒心や攻撃性が強いとされ、巣に近づくと威嚇して刺される危険があります。繁殖期の7月~9月は、特に注意が必要です。
巣は、木の枝や家の軒下など比較的目立つ場所に作られるケースが多く、主に毛虫や青虫などを捕食するため、庭木や農作物の害虫駆除に役立つ側面もあります。
ただし、巣が人の生活圏に近いため、攻撃されるリスクは高く、刺激すれば刺される点はスズメバチと共通しています。
キアシナガバチ|脚が黄色い

次に、キアシナガバチを紹介します。
| 生息地 | 沖縄~北海道。低山地に多い。 |
|---|---|
| 活動時期 | 4~10月 |
| 大きさ | 21mm~26mm |
| 特徴 | 全体的に黄褐色で脚が黄色い 巣は開放的な場所に作られることが多い 攻撃性が比較的高く注意が必要 |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:高い 攻撃性:高い |
キアシナガバチは、その名の通り黄色い脚が特徴的なアシナガバチです。比較的温暖な地域でよく生息していて、体長は働きバチで約21〜26mmほどとやや大型。体は黒褐色に黄色い模様が入ります。見分ける際は鮮やかな黄色い脚に注目するとよいでしょう。
庭木や建物の隙間などに、紙のような素材を唾液で固めて形成されたシャワーヘッド状の巣を作ります。
性格は、セグロアシナガバチ同様、アシナガバチの中でもやや攻撃的とされ、人が近づきすぎると威嚇行動を取り始めます。
一方で、毛虫やハエなどを捕食する益虫としての側面も強く、自然環境や農業の場では重要な存在です。
フタモンアシナガバチ|腹部の2本線が特徴

フタモンアシナガバチは、腹部に2本の黄色い帯状模様があるのが名前の由来です。
| 生息地 | 沖縄~北海道 |
|---|---|
| 活動時期 | 4~11月 |
| 大きさ | 12mm~18mm |
| 特徴 | 翅に2本の黒帯模様がある 体色は黄褐色でやや小型 人家周辺や軒下に巣を作りやすい |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:普通 攻撃性:低い |
働きバチの体長は12〜18mmほどで、アシナガバチの中では中型にあたります。
巣は、木の枝や建物の軒下など、比較的開けた場所に作られるので、見た目的にも判別しやすいでしょう。
温和な性格とされ、こちらから近づいたり刺激したりしなければ攻撃される危険性はあまりなく、他の種類よりも人とのトラブルは少ない傾向にあります。
ただし、繁殖期や巣に脅威を感じたときには攻撃態勢に入るので、油断は禁物ですよ。
トガリフタモンアシナガバチ|東部がとがっている
トガリフタモンアシナガバチという種類も生息しています。
| 生息地 | 北海道、秋田県 |
|---|---|
| 活動時期 | 5~9月 |
| 大きさ | 14mm~19mm |
| 特徴 | 頭楯(とうじゅん)の前縁が鋭く尖っている 胸部の斑紋が比較的大きめ 分布域が限定的で、自然環境に営巣しやすい |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:普通 攻撃性:低い |
トガリフタモンアシナガバチは、フタモンアシナガバチと非常に近縁で似ていますが、識別の鍵となるのが頭楯前縁の形状です。トガリフタモンは、頭部が鋭く尖っているのが名前の由来にもなっています。
胸部や腹部にある斑紋(黄色や黒色の模様)も、フタモン種と比較してやや大きめに見えるでしょう。体長としては、他のフタモン系とほぼ同じく14~19mm程度。
営巣場所は、主に河原や草地、笹藪などの自然環境を選ぶ確率が高く、人間生活圏にはあまり営巣しない傾向があります。分布域も限定されていて、北海道などの寒い地域での確認例があります。
キボシアシナガバチ|腹部に黄色紋

次に、キボシアシナガバチの紹介です。
| 生息地 | 沖縄~北海道 |
|---|---|
| 活動時期 | 5~10月 |
| 大きさ | 12mm~18mm |
| 特徴 | 腹部第一節に黄色紋がある 巣房の蓋が鮮やかな黄色 地上1~2メートル付近の低木や木の葉裏に営巣 |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:高い 攻撃性:高い |
キボシアシナガバチは、働きバチで体長がおよそ12~18mm程度と小型~中型に分類されます。全体に黒褐色の地味な体色ながら、腹部第一節に一対の黄色紋が見られるのが識別の手掛かりです。
体の黄色紋だけでなく、巣房を覆う蓋、つまり繭を覆う部分が鮮やかな黄色である点も特徴的。
生息域は日本全国で、低木の枝先や葉の裏、地上約 1~2 メートル程度の高さの比較的低い場所を好んで営巣します。
ヤマトアシナガバチ|人家周辺に多い

続いて、ヤマトアシナガバチについて解説します。
| 生息地 | 沖縄~本州北部 |
|---|---|
| 活動時期 | 4~10月 |
| 大きさ | 15mm~22mm |
| 特徴 | 日本全域に広く分布 黄褐色で模様がはっきりしている 民家の周辺や庭木に巣を作る |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:低い 攻撃性:低い |
ヤマトアシナガバチは、日本全国に広く分布するアシナガバチで、人家の軒下やベランダ、庭木など身近な場所によく巣を作ります。
働きバチの体長は約15〜22mmで、全体的に黒褐色に黄色い模様があり、スズメバチよりも細長い体型が特徴。
ヤマトアシナガバチは比較的温和な性格ですが、巣に近づいたり刺激したりすると攻撃され、刺されると強い痛みを伴います。
庭木や畑の害虫である毛虫や青虫を捕食するため、自然界では益虫として重要な役割を果たしている一方で、生活圏に営巣するケースが多いのは注意すべき点。
巣が、ベランダや玄関付近にできた場合は、早めの対応が望まれます。
コアシナガバチ|体が小さい
次に、コアシナガバチの解説をします。
| 生息地 | 九州~北海道 |
|---|---|
| 活動時期 | 4~10月 |
| 大きさ | 11mm~17mm |
| 特徴 | 小型で黒褐色に黄色の模様が入る 攻撃性は比較的弱い 林縁や低木によく営巣する |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:高い 攻撃性:高い |
コアシナガバチは、その名の通り、働きバチの体長が11〜17mmほどと小型の種類で、日本各地に分布しています。体色は黒褐色で黄色い模様がありますが、全体的に他のアシナガバチに比べて控えめな印象です。
営巣場所も、木の枝や建物の隙間など、比較的目立たない場所に作られる傾向があります。性格は温和で、人が巣に極端に近づかない限り攻撃してくることは少ないでしょう。
小型ながらも毛虫や蛾の幼虫を捕食し、自然界では重要な益虫です。刺されるリスクは低めですが、巣が生活空間に近い場合は油断せず、早めの駆除を検討してください。
ヒメホソアシナガバチ|小型で細身
ヒメホソアシナガバチという細身のタイプも存在します。
| 生息地 | 沖縄~本州北部 |
|---|---|
| 活動時期 | 4~10月 |
| 大きさ | 11mm~16mm |
| 特徴 | 体長が小さく、細身で華奢な体形 腹部に細い黄色帯が入る 市街地でも見られる |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:低い 攻撃性:高い |
ヒメホソアシナガバチは、体長が約11〜16mmと小型で、体型も細長いのが特徴。小さな体で活動的に飛び回ります。体色は黒褐色に黄色い模様がありますが、他種よりも色が薄めで目立ちにくいでしょう。
日本各地に分布し、低木や建物の隙間など比較的目立たない場所に巣を作ります。毒性は強くないものの、巣を揺らしたり刺激したりすると一斉に襲ってくるので、絶対にやめましょう。
毛虫やアブラムシなどを捕食して庭木の健康を守るため、自然界においては益虫として重宝されます。
ムモンホソアシナガバチ|斑紋がない

ムモンホソアシナガバチという種類も見ていきましょう。
| 生息地 | 九州~本州 |
|---|---|
| 活動時期 | 4~10月 |
| 大きさ | 15mm~20mm |
| 特徴 | 翅に特徴的な黒帯模様がない 細身でやや小型のアシナガバチ 林縁や草地など自然環境に営巣 |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:低い 攻撃性:高い |
ムモンホソアシナガバチは、腹部に目立った斑紋がなく、全体的に黒っぽいのが名前の由来です。働きバチの体長は15〜20mmほどで、スリムな体型をしています。
日本全国に広く分布し、山林や農地、都市部の庭先などでも確認されます。巣は木の枝や軒下に作られ、他のアシナガバチと同様にシャワーヘッド型です。
性格はやや警戒心が強く、巣に近づくと早い段階で攻撃態勢にはいります。刺されると強い痛みを伴うため、特に巣が人家の近くにある場合は早めの駆除が必要になるでしょう。
オキナワチビアシナガバチ|南西諸島に分布

オキナワチビアシナガバチという種類も存在します。
| 生息地 | 琉球諸島 |
|---|---|
| 大きさ | 9mm~10mm |
| 特徴 | 体長が非常に小さい 葉の裏に小型・縦長の巣を作る 南西諸島(沖縄諸島など)を中心に分布 |
| 毒性・攻撃性 | 毒性:弱い 攻撃性:低い |
オキナワチビアシナガバチ は、国内では主に南西諸島(沖縄やその周辺)で見られる小型のアシナガバチで、体長は約9~10mm程度と非常に小さいのが特徴です。
ススキやサトウキビ、チガヤ、ソテツなどの葉の裏側に、縦長または細長い形で、雨露を避けるようにひっそりと営巣します。
巣はあまり大きくならず、育房数が少ない傾向にありますが、草刈りや農作業などで意図せず巣に近づいて刺されるリスクも意外に多く見受けられます。
沖縄県などの暖かい地域に限定して分布しているため、本州などではほとんど見られない種類です。
ナンヨウチビアシナガバチ|総合対策外来種
最後に、ナンヨウチビアシナガバチを紹介します。
| 生息地 | 硫黄島(外来種) |
|---|---|
| 大きさ | 14mm~15mm |
| 特徴 | 濃赤褐色の体色 腹部第一節が細く柄状 外来種として日本には限定的に定着 |
ナンヨウチビアシナガバチ は、東南アジアやマリアナ諸島が本来の分布地域。日本では硫黄島など限られた地域で確認されている外来種です。
女王バチは約17mm、働きバチは14~15mm程度と中型寄りの体格を持ち、体色は濃赤褐色。腹部には幅広い黄色の帯状斑紋が見られます。腹部第一節が細く柄状になる点も、他の日本産アシナガバチと区別する要素です。
繁殖すると大規模になりやすく、育房数が 1,000を超えるような巣が形成される場合もあり、今後日本に定着した場合には、生態系への影響や在来種との競合が懸念されています。
「アシナガバチ」と名が付くにもかかわらず、実はスズメバチ科である種類も、上記以外に複数存在します。個性はあるものの、スズメバチと近しい生態であるのが伺えますね。
アシナガバチを見かけた時の対処法

アシナガバチにはさまざまな種類が存在しますが、巣は比較的目立ちやすい場所や形で現れます。そこで、アシナガバチや巣を見かけた時にすべき対処法を解説します。
- 不用意に近づかず刺激しない
- 巣の場所を確認して距離を取る
- 専門業者に相談して駆除を依頼する
それぞれ念頭に置きましょう。
不用意に近づかず刺激しない
アシナガバチは、スズメバチに比べて比較的攻撃性が弱いと言われますが、巣や仲間を守るためには、鋭い針で刺す場合も少なくありません。
特に、巣の周囲では警戒心が強まるため、近づいたり大きな音や振動を与えると刺激となり危険です。
刺されると、強い痛みや腫れだけでなく、アレルギー反応を起こす人もいるほど。見かけた場合は決して手で払ったりせず、静かにその場を離れてください。
巣の場所を確認して距離を取る
アシナガバチは、軒下や植木鉢の裏など、人が生活する場所に巣を作る傾向にあるため、もし巣が出来ている兆候があるなら、巣の位置を可能な限り把握しておきましょう。
巣の場所を特定しておかないと、気付かぬうちに近づいてしまい、思わぬ攻撃を受けかねません。
巣を確認できたら、常に2~3メートル以上距離を保ち、子どもやペットを不用意に近づけないように注意してください。
巣の場所が目視できない時は、無理せず業者に特定を依頼しましょう。
専門業者に相談して駆除を依頼する
アシナガバチの巣は、初期段階であれば自力で取り除けるケースもありますが、安全面を考えると専門の駆除業者に依頼するのが確実です。
特に、床下や室外機の奥などの難所に巣がある場合は、安全面や手間を考慮すると業者に依頼したほうがコストパフォーマンスが上がるでしょう。
「ハチ駆除専門クリーンライフ」にお気軽にご相談ください!
アシナガバチの種類によっては自分で駆除も可能

アシナガバチなら自分で駆除できるのか、気になる方もいるでしょう。そこで、自分で駆除できるケースをリストアップしました。
- 攻撃性が比較的弱い種類
- 巣が数センチ程度で初期段階
- 早朝や夜間に作業できる
- 安全確保ができる場所に巣がある
- 防護服や防護具を用意できる
攻撃性が低い種類、かつ巣がまだ小さい段階であれば、自分で駆除できる可能性があります。以下手順を参考にしてみてください。
<手順>
- 長袖・長ズボン・手袋・帽子・マスクなどで身体を防護する
- 蜂駆除スプレーを巣に直接噴射する
- 15分ほど放置して蜂の様子を見る
- 巣の動きがなくなったら、再度駆除スプレーを撒き、一晩置く
- 翌朝巣を確認し、死骸やかけらを除去する
- 巣のあった場所を清掃する
- 忌避剤を撒き、再発防止対策する
詳しい駆除方法や自力で巣を駆除する時の注意点は、以下の記事にまとめています。あくまでも、安全第一が大前提。少しでも不安がある場合は、専門業者に連絡してください。
アシナガバチ駆除を業者に依頼するメリット

ここで、アシナガバチ駆除を業者に依頼するメリットをご紹介します。
- 安全に駆除できる
- 蜂の種類や特性ごとに効率的に作業できる
- 再発防止対策で長期的な安心につながる
それぞれ、参考にしてください。
安全に駆除できる
アシナガバチの駆除は、刺される危険と隣り合わせ。比較的穏やかな種類のアシナガバチでも、そのリスクは避けられません。
その点、専門業者は、プロならではの道具や技術を駆使して、蜂の動きに応じた安全な方法で駆除を進めます。
特に、巣が大きく成長している場合や高所や手の届きにくい狭い場所にある時には、無理せず専門の駆除業者に依頼する方が得策です。
蜂の種類や特性ごとに効率的に作業できる
アシナガバチは、種類や巣の場所によって行動パターンや警戒心の強さが異なります。
飛び回る蜂を目の前に、瞬時に種類を判別するのは、素人にとって至難の業。蜂を無駄に刺激して、近隣にまで悪影響を及ぼすケースも少なくありません。
プロの業者であれば、蜂の種類を見極めつつ、巣の構造や規模に応じた方法で効率的に作業を完了できます。
場数を踏んでいるため、失敗による二次被害も防げるのも安心ポイントです。
再発防止対策で長期的な安心につながる
アシナガバチの特性として、巣を駆除したとしても、あえて同じ場所や近くに再び巣を作るケースが多く見受けられます。
一度営巣した場所は、安全であると認知されてしまうので、駆除後の再発防止が、その後の安全性に大きく影響するのです。
業者は、巣を除去するだけでなく、周囲に残った蜂や卵を取り除き、痕跡を徹底的になくします。さらに、再発を防ぐための薬剤処理まで実施してくれるため、市販の防虫スプレーよりはるかに再発する確率を下げられるでしょう。
単なる一時的な駆除ではなく、将来的な安心にもつながる点が、プロの業者に依頼する大きなメリットと言えます。
「ハチ駆除専門クリーンライフ」にお気軽にご相談ください!
アシナガバチ駆除を業者依頼する費用相場

最後に、駆除業者に依頼する場合の費用相場を解説します。
| 作業メニュー | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般的なアシナガバチの巣除去 | 10,000円~20,000円 | 巣が低所・規模が小さい場合の一般的相場 |
| 難所・高所設置 | +3,000円~20,000円 | 高所作業・足場使用・壁内・軒下奥・室外機内部など、状況によって変動 |
| 大規模な巣駆除 | 20,000円前後 | 事業用途など対外的な場所での駆除 |
基本的に、アシナガバチの種類によって価格が変動するケースは少ないでしょう。追加料金が加算されて費用がかかりやすいのは、高所や難所に巣がある場合。難易度の高い作業内容に比例して、人件費や足場設置費用などが加算されます。
蜂駆除の相場は、以下記事で詳しく解説しています。
アシナガバチを見かけたら種類問わず『ハチ専門駆除クリーンライフ』に相談!
「ハチ駆除専門クリーンライフ」にお気軽にご相談ください!
アシナガバチの種類について、それぞれの特性や駆除方法などをご紹介しました。
スズメバチより攻撃性が低いと言われているアシナガバチでも、油断すると刺されたり怪我したりするリスクは変わりません。スズメバチ同様にアレルギー反応が出るケースもあるので、油断は大敵。
蜂が飛び回っている時や巣が既に大きく成長している場合は、専門業者に駆除してもらうのが一番安全でしょう。
『ハチ駆除専門クリーンライフ』は、蜂の種類や巣の大きさにかかわらず、迅速に蜂の巣を駆除します。自分ではチャレンジしづらい高所や難所も迅速に対処しますので、ぜひお気軽にご相談ください!
アシナガバチの種類に関するよくある質問
- アシナガバチにはどのような種類が存在しますか?
- 日本では、アシナガバチ属・ホソアシナガバチ属・チビアシナガバチ属の3属に分類されるアシナガバチが、主に11種類生息しています。
種類ごとに体の模様や色に違いがあり、巣の作り方や攻撃性の強さも異なります。
- どの種類のアシナガバチが一番危険ですか?
- 特に攻撃性が強いとされるのは、セグロアシナガバチ。巣に近づくと積極的に防衛行動を取る傾向があります。
ただし、ほかの種類でも刺激すれば刺されるリスクは変わりません。種類に関わらず、巣を見つけたらすぐに対処してください。
- アシナガバチの種類によって刺されたときの痛みは違いますか?
- 種類によって毒性の強弱はありますが、基本的に刺されると痛みと腫れを伴うのは共通です。体格の大きい種類ほど針も太く、刺されたときの痛みが強いと感じるでしょう。
いずれにせよ、刺された場合は冷却や医療機関の受診が必要です。
- 体の色で種類を見分けられますか?
- 種類によって、体色や模様に特徴があります。
セグロアシナガバチは黒っぽく、キアシナガバチは黄色い脚が目立つ、というように名前にも反映されています。
大きさも種類ごと差があるので、見た目でおおまかな判別はできるでしょう。
- どの種類が庭に巣を作りやすいですか?
- 都市部や住宅の庭でよく見られるのは、セグロアシナガバチやヤマトアシナガバチが多いでしょう。
人との距離が近くなりやすく、無意識に刺激してしまうケースが多いので、早めに駆除するのが得策です。
危険ですので、無理せず
まずはプロに相談を!
- お支払い方法
-
- 現金払い

- 各種クレジットカード対応

- コンビニ後払い

- 銀行振込

- QR決済