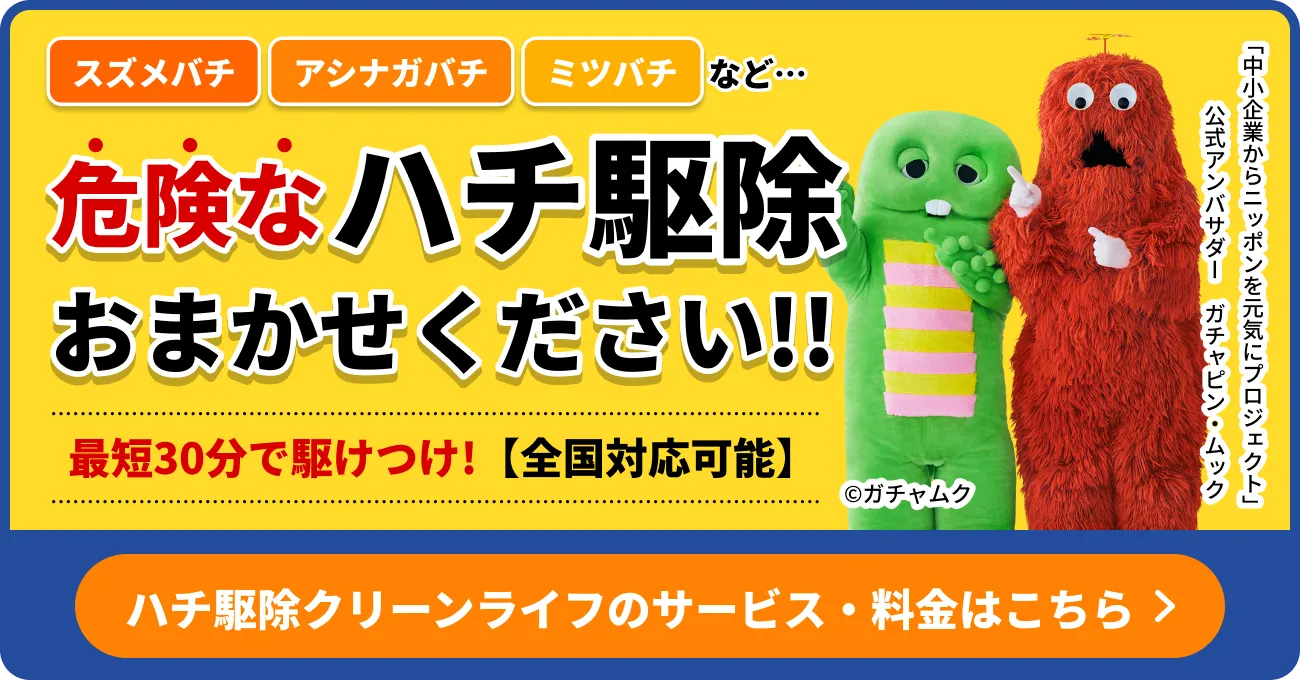- トップ
- アシナガバチの危険性を知ろう!毒の特徴や刺された時の正しい対処法

アシナガバチの危険性を知ろう!毒の特徴や刺された時の正しい対処法
スズメバチより穏やかと言われるアシナガバチ。危険性も低いと思っていませんか?
本記事では、アシナガバチの危険性に着目して、詳しく解説していきます。
- 「アシナガバチにも毒はあるの?」
- 「刺されたら危険なの?」
などの疑問に向けて、アシナガバチの特徴や危険性を高める条件、刺されたときの対処法などをまとめました。アシナガバチだからと言って油断せず、正しい知識で身を守りましょう。
Contents
アシナガバチが持つ危険性とは

最初に、アシナガバチが持つ危険性に基づいて、特徴やスズメバチとの違いを解説していきます。
アシナガバチの特徴
アシナガバチは、体長が比較的小さく、後脚が長くぶら下がるように飛びます。体色は黄色と黒の縞模様が特徴。軒下・庭木・植え込みなど、人間の生活圏にも近い場所に巣を作ります。
性格としては、刺激を与えなければ攻撃してくる恐れは低く、「益虫」として毛虫やイモムシを捕食する側面もあります。ただし、活動が活発になる夏から初秋にかけては巣が大きくなり、防衛行動が強まるため、近づいたり巣を刺激すると刺されかねません。
スズメバチとの違い
スズメバチは、体型がずんどうで、外見からして、アシナガバチに比べ明らかに迫力のある姿をしています。
巣の形状にも顕著な違いがあります。スズメバチの巣はとっくり型や球形で厚い外殻に覆われ、出入り口が一つで見づらいのが特徴である一方で、アシナガバチの巣は屋外の見える場所に設置され、中がむき出しのシャワーヘッド状です。
性格面でも、警戒心や攻撃性が強いとされるスズメバチに対して、アシナガバチは比較的おとなしく、こちらから刺激しなければ攻撃に発展しにくいとされています。
とはいえ、どちらも毒を持つ点では変わりがないので、注意すべき点は同等です。
スズメバチとアシナガバチの違いは、以下の記事で詳しく解説しています。
アシナガバチの毒に潜む危険性

続いて、アシナガバチの毒に潜む危険性をお伝えします。毒に含まれる成分や、アレルギー発症につながる理由を見ていきましょう。
毒に含まれる成分
アシナガバチの毒に含まれる成分を、以下の表にまとめました。
| 成分名 | 主な作用・特徴 |
|---|---|
| ヒスタミン | 血管拡張やかゆみ、痛みを引き起こす |
| セロトニン | 神経刺激により痛みや炎症、血管収縮を引き起こす |
| ハチ毒キニン | 神経を刺激して痛みや炎症を引き起こす |
| マストパラン | 肥満細胞を刺激し、ヒスタミン放出を促進する |
| ポリアミン | 細胞膜の透過性を高め、毒を拡散する |
| ヒアルロニダーゼ | 組織を分解して、毒を拡散する |
| アンチゲン5 | アレルゲンとして作用 |
ハチ毒にはこのように多種の成分が含まれており、それぞれが異なるメカニズムで体内に作用します。
アレルギー発症につながる根拠
アシナガバチの毒によるアレルギー発症は、主に免疫系が毒成分を「異物」と誤認し、過剰に反応する背景があります。
初回の刺傷時に体が成分を記憶するので、再び刺されると抗体が反応して、「アナフィラキシー反応」が引き起こされるのです。
症状の強さは個人差が大きく、刺傷の回数や体質に左右されますが、一度でも強いアレルギー反応を起こした場合は、次回以降の刺傷で重症化するリスクが高まるため、速やかに医療機関にかかりましょう。
アナフィラキシーショックとは
アナフィラキシーショックとは、ハチ毒などに対して体が過剰に反応し、短時間で全身に重い症状が出る危険なアレルギー反応です。刺されて数分以内に、息苦しさ、動悸、めまい、全身のじんましん、顔や喉の腫れ、血圧の急低下などが起こります。
放置すると命に関わるため、すぐに救急要請が必要です!
アナフィラキシーの参考文献
アシナガバチに刺された時の症状別危険度

では、もしアシナガバチに刺された時の、症状別に危険度をチェックしていきましょう。
レベルごとに、解説していきます。
【危険度1】痛み・赤み・腫れ・かゆみ
アシナガバチに刺されると、刺された直後から刺し口付近にズキッとした痛みを感じ、赤みや腫れが現れます。腫れなどの局所症状は、ハチ毒の刺激による典型的な反応で、多くの場合数時間〜1日程度で落ち着くでしょう。まずはしっかり洗浄・冷却して、様子を見てください。
【危険度2】熱感、硬さ
刺された部位がさらに熱を持ち、腫れた部分が固くなるようなら、局所反応が強まっているサインです。肌表面だけでなく組織深部にまで炎症が及んでいる恐れがあり、そのまま腫れ上がるケースも多く見受けられます。
そのまま痛みが長引いたり、熱感が継続したりする場合は、医療機関に相談しましょう。熱感・硬さが全身に影響を与えると、かなりリスクが高い状態になりかねません。
【危険度3】ショック症状
刺されてから数分〜数十分の間に、以下のような症状が出たら要注意。
<息苦しさ・動悸・意識の低下・血圧低下・喉の腫れ・全身のじんましんなど>
アナフィラキシーショックの恐れがあり、命に関わる緊急事態なので、速やかに救急車を呼んでください。
特に、過去にハチ刺されで強い反応を起こした人や複数箇所刺された人は、1回で症状が急速に進行するので、少しでも違和感を感じたら即医療機関へ向かうべきです。
アシナガバチの毒による危険性が高まる条件

ここで、アシナガバチの毒によって、危険性が高まる点を挙げました。
- アレルギー体質である
- 過去に刺傷歴がある
- 複数刺された
- 免疫力がない(高齢者・子どもなど)
- 口で吸うなどの間違った応急処置
アシナガバチの毒は充分危険。しっかりとリスクを把握しておきましょう。
アレルギー体質である
普段から、食物アレルギーや喘息などのアレルギー疾患を抱えている場合、ハチ毒に対する抵抗力が下がっているかもしれません。
アシナガバチに刺された時に体内に抗体が存在していると、刺された直後に全身に反応を起こす「アナフィラキシー」のリスクが上がります。アレルギー体質の人は、通常より慎重な対応すべきと言えるでしょう。
過去に刺傷歴がある
一度でもハチに刺された過去があると、体内にハチ毒に対する抗体が生成されている確率が高いと言われています。
再度刺された際、この抗体が反応し、通常の刺傷よりも強いアレルギー反応を引き起こす恐れがあるので、過去の刺傷経験がある場合は、少しの刺傷でも医療対応を検討してください。
複数刺された
一度に複数箇所を刺されると、体内に取り込まれる毒の量が多くなり、局所反応だけでなく全身への影響が出やすくなります。
また、多量の毒によって免疫システムが急激に反応し、アレルギー反応やアナフィラキシー症状の発症確率が上がります。
一見、大した症状がでない場合でも、複数刺された時点で医療機関に相談しましょう。
免疫力がない(高齢者・子どもなど)
高齢者や小児、また体調を崩しているときなど、免疫力が低下している状態では、ハチ毒に対して適切な防御反応が働きにくくなります。
免疫系が弱まっていると、毒の作用を抑えきれず、症状が長引いたり重篤化したりするリスクが否めません。特に、高齢者は合併症が起こるリスクもあるため、刺されただけでも慎重に判断すべきです。
口で吸うなどの間違った応急処置
刺された後に、口で毒を吸い出す動作を映画などで見かけますが、実際は間違った応急処置です。口内から細菌が入り込むリスクや、毒が吸引されて余計に血中に入る危険があるので、絶対に止めましょう。
正しい応急処置は、しっかり洗浄して冷却するのが基本です。誤った処置が遅延や重症化につながる点をしっかり認識しておきましょう。
アシナガバチの危険性を回避する刺傷時の応急処置

では、その後の名案を分けかねない正しい応急処置法をご紹介します。以下の手順を参考にしてください。
- 針が残っていればピンセットで抜く
- 患部を流水でよく洗い流す
- 冷水や保冷剤で冷やす
- 市販の抗ヒスタミン外用薬を塗布する
- じんましんなどが出る場合は至急医療機関へ
アシナガバチに刺されたら、まず針が表面に残っていればピンセットで慎重に抜きましょう。その後流水でしっかり洗い、毒や汚れを落としてください。それから冷却すると、腫れや痛みが和らぐはずですが、市販の抗ヒスタミン外用薬を塗っておくとさらに安心です。
万が一、全身にじんましんや呼吸のしにくさ、めまいなどが出た場合はアナフィラキシーの可能性があるため、速やかに医療機関にかかってください。
アシナガバチの駆除方法

さて、危険性のあるアシナガバチには、刺されない環境が一番大切。そこで、アシナガバチの駆除方法をご紹介します。
巣の場所や状態によって、駆除方法を決めてください。
自分で駆除する方法
もし、アシナガバチの巣が特定できて、かつあまり大きくない大きさであれば、自身で駆除できる可能性があります。
もちろん、小さいからと言って油断は禁物なので、以下の揃えるべき道具や正しい手順をしっかりチェックしてください。
<事前に揃える道具>
- 蜂用の殺虫スプレー
- 防護服(なければ厚手の長袖・長ズボン・レインコートで代用)
- マスク・ゴーグル
- 軍手
- 長靴
- 脚立または踏み台(高所の場合)
<手順>
- 夕方から夜間の時間帯に駆除計画を立てる
- 防護服でしっかり素肌や目を保護する
- 巣から適度な距離を保ち、殺虫スプレーを噴霧する
- 一晩置き、翌日蜂の動きがないか確認する
- 巣の中の蜂が全滅していたら巣を除去する
- 巣だけでなく、死骸もあわせてゴミ袋で密封する
- 蜂の巣があった場所に再度念入りにスプレーする
巣で休んでいる個体が多くなる夕方から夜間の時間帯を狙って、一気に噴射するようにしてください。市販で強力な蜂用殺虫スプレーを購入できますが、中身がなくなるのも早いため、複数本用意しておきましょう。
小さな蜂の巣を駆除する際のポイントは、以下記事で詳しく解説しています。
専門業者に駆除を依頼する方法
すでに巣が大きかったり蜂の数が多かったりする場合は、蜂駆除専門の業者に駆除を依頼しましょう。
蜂駆除の場数を踏んでいる専門業者は、巣の位置や規模、周囲の環境に応じて最適な方法を使い分けて、迅速に対処してくれます。単なる撤去にとどまらず、再発防止対策も実施してくれるので、長期的な視点からも安心感のある方法です。
『ハチ駆除専門クリーンライフ』なら、無料で見積もり対応していますよ。
「ハチ駆除専門クリーンライフ」にお気軽にご相談ください!
安心できる駆除サービスについては、以下の記事を参考にしてください。
アシナガバチの危険性を抑える予防策

最後に、アシナガバチによる被害を抑える予防策をお伝えします。
- 巣を作らせない環境をつくる
- 忌避スプレーを活用する
- 定期的に点検を依頼する
上記3点、それぞれ参考にしてください。
巣を作らせない環境をつくる
アシナガバチは、春から初夏にかけて巣を作り始めます。巣を作らせないためには、家屋の軒下や屋根裏、ベランダなど、巣が作られやすい場所の環境を整えましょう。すき間を塞いだり庭木を選定したりするだけでも効果的。
アシナガバチは、室外機の内部に営巣するケースもあるので、ベランダにエサになりそうなジュースの残りなどを放置しておかないようにするのも大切です。
蜂の巣ができやすい家の特徴や予防策は、以下の記事を参考にしてください。
忌避スプレーを活用する
忌避スプレーを活用するのも、アシナガバチを寄せ付けないための手軽な方法。アシナガバチが嫌う成分を含んでいるので、巣の周辺や家屋の周囲に散布するだけで侵入を減らせるでしょう。
風の強い日や雨の日は効果が薄れるため、天候を考慮して使用するのがポイントです。
定期的に点検を依頼する
アシナガバチは、人間の生活圏に近いエリアに巣ができやすい傾向にあります。春から夏にかけて、こまめに点検すると巣の早期発見につながります。
定期的に、専門業者に点検を依頼するのもおすすめ。素人は気付けないような場所の巣を発見したり、そのまま駆除したりできるので、大事に至る前に解決できるでしょう。
アシナガバチは危険性大!刺されないように日常から予防しよう!
「ハチ駆除専門クリーンライフ」にお気軽にご相談ください!
アシナガバチの危険性について、生態や毒の成分、危険度が増す条件などをまとめました。
スズメバチと比べると穏やかとされるアシナガバチですが、防衛本能は引けを取りません。もしアシナガバチが身近に出現したなら、油断せずに、早めに対処するようにしてください。
アシナガバチの駆除作業や巣の点検は、実績豊富な『ハチ駆除専門クリーンライフ』がおすすめです。
現地確認や見積もり作成は無料で対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください!
アシナガバチの危険性に関するよくある質問
- アシナガバチは本当に危険なのですか?
- アシナガバチは、基本的に攻撃性は低いものの、刺されると痛みや腫れを伴います。アレルギー体質の人や過去に刺された経験がある人は、重篤な反応を起こす恐れがあるので、油断は禁物。
複数箇所刺された場合や、免疫力の低い高齢者・子どももリスクが高い傾向にあるので、適切な対処が重要です。
- スズメバチと比べてアシナガバチの危険性はどう違いますか?
- アシナガバチは、スズメバチに比べると攻撃性は低めです。しかし、刺されると痛みや腫れが生じ、アレルギー体質の人や複数箇所刺された場合は命にかかわる症状が出るケースも否めません。
スズメバチほど死亡例は少ないものの、油断せず予防と迅速な対応が重要です。
- アシナガバチは何月ごろに危険性が高まりますか?
- アシナガバチは、春先に女王バチが巣作りを始め、初夏から夏にかけて巣が大きくなり活動が活発化します。特に7月〜9月は働きバチの数が増え、攻撃性や刺傷リスクが高まる時期です。
庭やベランダ、軒下をこまめに点検すると同時に、もし巣を見つけたら距離を保ちつつ業者に連絡してください。
- アシナガバチは自分から襲ってくるのですか?
- アシナガバチは、基本的に人を襲う習性はなく、巣を守る防衛本能で刺すケースがほとんどです。
普段はおとなしく、刺激しなければ刺される危険は低いですが、巣に近づいたり、急に手を振るなど刺激を与えると攻撃してくる可能性があるので、巣周辺では注意が必要です。
- アナフィラキシーショックはどんな人に起こりやすいですか?
- アナフィラキシーショックは、ハチ毒に対する抗体を持つ人に起こりやすく、特に過去に刺された経験がある人やアレルギー体質の人にリスクが高まります。
もちろん、それ以外の方でも体内で反応する抗体がないとは限らないので、少しの刺傷でも必ず迅速に対処しましょう。
危険ですので、無理せず
まずはプロに相談を!
- お支払い方法
-
- 現金払い

- 各種クレジットカード対応

- コンビニ後払い

- 銀行振込

- QR決済