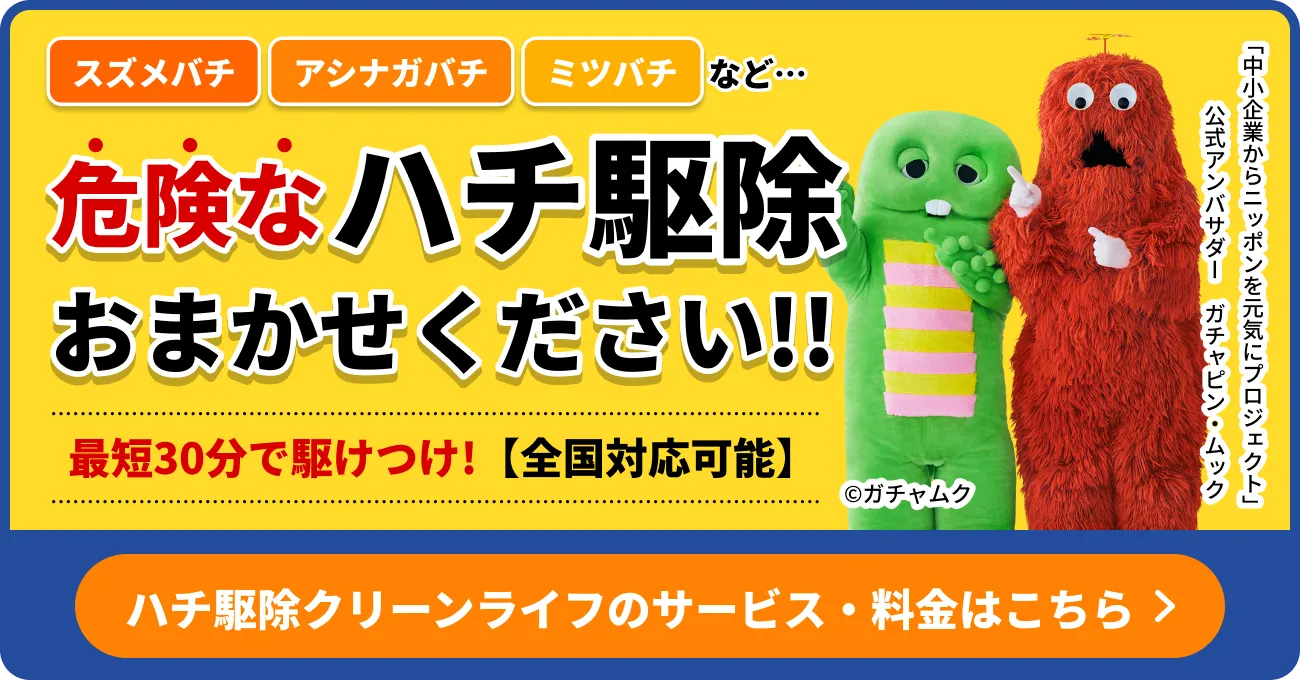- トップ
- スズメバチの天敵まとめ|自然界の生物11種と最適な駆除方法を紹介

スズメバチの天敵まとめ|自然界の生物11種と最適な駆除方法を紹介
鳥類・昆虫類・哺乳類などに分類されるスズメバチの天敵を11種ご紹介します。
スズメバチは刺されると大きな痛みやアレルギー反応を引き起こすこともあり、大変危険な存在として知られていますが、実は凶暴なスズメバチにも“天敵”が存在しています。
スズメバチの天敵だけでなく、安全な駆除方法についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
スズメバチの天敵 早見表
以下は、スズメバチの主な天敵11種を生物の分類ごとに一覧にした早見表です。
| 分類 | 天敵の名前 | 特徴 |
|---|---|---|
| 鳥類 | ハチクマ | スズメバチの巣を狙って襲撃する猛禽類 |
| モズ | 小型ながら獰猛、昆虫や小動物を捕食 | |
| ニワトリ(海外) | アジアの一部地域では野生化し昆虫も捕食 | |
| 昆虫類 | オオカマキリ | 前脚でスズメバチを捕らえそのまま捕食 |
| オニヤンマ | トンボの中で最大種、スズメバチを襲って捕食 | |
| シオヤアブ | 奇襲型の捕食者、毒針に強くスズメバチも狙う | |
| ギンモンシマメイガ | スズメバチの巣に寄生し、内部から破壊 | |
| 同属種 | オオスズメバチ | 他のスズメバチの巣を襲い幼虫を捕食 |
| チャイロスズメバチ | キイロスズメバチの巣に入り込み乗っ取る | |
| 哺乳類 | クマ | 巣ごと壊してサナギや幼虫を食べる |
| 人間 | ハチの子を珍味として食べる文化もある |
各天敵の詳細は、以下の項目でくわしく解説します。
鳥類に分類されるスズメバチの天敵

昆虫を食べることが多い「鳥類」の中には、危険なスズメバチを捕食する種類も存在しています。
以下では、スズメバチをエサとする3種の鳥をご紹介します。
巣を襲撃するタカ科の鳥 “ハチクマ”

ハチクマはスズメバチを主食とするタカ科の渡り鳥で、日本の夏季に山間部の森林で見られ秋になると東南アジアへ渡っていきます。
ハチを食べることと、同じ猛禽類のクマタカに似ていることから、鳥類でありながら“ハチクマ”という名前が付けられています。
ハチクマがスズメバチを捕食できるのは、全身を覆っている堅い羽毛でスズメバチの毒針を防ぐことができるためです。
その天然の防具と鋭い爪・くちばしを使ってスズメバチの巣を壊し、幼虫やサナギを食べます。なお、成虫はほとんど食べることはありません。
またハチクマはスズメバチが嫌うフェロモンを発しているとも言われており、巣を襲われたスズメバチはその臭いで戦意喪失するようです。
さらに、猛禽類として珍しく集団狩りを行う特殊な生態を持ち、自然環境においてスズメバチの数を調整する重要な役割を果たしています。
小型だが小鳥も襲うことがある ”モズ”

モズは体長20cmほどでスズメより一回り大きいかわいらしい小型の野鳥ですが、その性格は意外にも獰猛です。
スズメバチを含む昆虫やトカゲやカエルだけでなく、小型の鳥なども捕食対象とする“猛禽類顔負け”のハンターでもあります。
モズは捕らえた獲物を木の枝などに突き刺す「はやにえ」と呼ばれる独特の習性で知られています。
この「はやにえ」は、餌の保存や求愛行動の一環ともされており、秋〜冬の森や林では、枝先に刺さったスズメバチの姿を見かけることもあります。
小さな体に似合わぬ攻撃力で、スズメバチにとっても無視できない天敵のひとつです。
アジアに生息する野生の ”ニワトリ (海外) ”

私たちにとって身近な存在であるニワトリ。
その祖先は、東南アジアに生息する「セキショクヤケイ(赤色野鶏)」というキジ科の野鳥です。
このセキショクヤケイを人間が飼い慣らし、長い年月をかけて品種改良を重ねた結果、今のニワトリが生まれたといわれています。
現代でもタイやミャンマーなどでは、野生のセキショクヤケイや、かつて飼われていたニワトリが野生化した個体が自然の中で暮らしています。
そうした“野生ニワトリ”は雑食性が強く、昆虫や小動物を積極的に食べており、スズメバチも捕らえて食べることがあるのです。
なお、基本的に餌に困らない環境にいる家畜のニワトリは、危険を冒してまでスズメバチを食べることはほとんどありません。
昆虫類に分類されるスズメバチの天敵

オオスズメバチなどは3~4センチと身体が大きく、危険な毒ハチと頑丈な顎を持っているため昆虫の生態系の中でも上位に君臨していそうに思われますが、実はさらに強い肉食性の昆虫も存在しています。
ここでは自然界で見られる代表的な“昆虫系の天敵”をご紹介します。
鋭い前脚でスズメバチを捉える ”オオカマキリ”

オオカマキリは、鋭いカマのような前脚で獲物を素早く捕らえ、強靱な顎で獲物をかみ砕いて捕食する、比較的身近に生息しているハンター型の昆虫です。
体長は10cm前後と大型で、バッタやチョウだけでなく、スズメバチのような攻撃的な昆虫さえも捕まえて食べてしまうことがあります。
目の前で動くものを高精度でとらえる能力と、獲物を逃がさない力強さは、自然界でも屈指の強さを誇ります。
また長く大きな鎌で押さえ込まれると、スズメバチの毒針や顎が届かず反撃できないというのも天敵である理由の1つです。
日本最大で最強の肉食トンボ ”オニヤンマ”

オニヤンマは日本で最大のトンボで、全長は10cmを超えることもある堂々たる存在です。
また、その飛行速度も最速で時速60km/h以上とも言われており、時速40km/h程度のスズメバチでは到底逃げ切れません。
さらに、トンボの動体視力は昆虫界でトップクラスを誇っており、遠くから獲物を見つけることにも長けています。
オニヤンマは狙いを定めるとスズメバチが毒針を構える前に背後や横から高速で奇襲し、空中で一気に仕留める狩りスタイルが特徴です。
その強さから、スズメバチだけでなく他の多くの昆虫もオニヤンマの特徴的な黒×黄色を本能的に警戒すると言われており、身に付けるだけで虫が逃げていく「オニヤンマ型の虫よけアクセサリー」まで登場しています。
枝葉に隠れて背後から奇襲する ”シオヤアブ”

シオヤアブは大きさが2~3cm程の大型のアブで、北海道から九州まで日本全国に生息しており割と身近な昆虫です。人間を襲うことはなく、近づくだけで逃げていきます。
シオヤアブには毒針はありませんが、鋭い口吻(こうふん)を獲物に突き刺して体液を吸い取ります。
シオヤアブは枝や葉に静かに止まり、獲物が近づいた瞬間に一気に飛びかかって捕獲する狩りスタイルで、空中を飛び回るスズメバチでさえ油断すればその餌食となります。
飛行能力も高く、スズメバチにも真正面からではなく“奇襲スタイル”で挑むため、返り討ちに遭いにくいのも特徴です。
なお、シオヤアブは先制攻撃には弱いため、逆に奇襲されスズメバチに捕食されることもあります。
巣に寄生し巣盤を食べる ”ギンモンシマメイガ”

ギンモンシマメイガは日本全国に生息しており、一見するとただの小さなガの仲間ですが、その幼虫はスズメバチの巣に“忍び込む”という、まさに寄生戦略で存在感を発揮します。
ギンモンシマメイガの成虫は、夜間の警戒の薄いタイミングでスズメバチの巣の中に卵を産み付け、ふ化した幼虫は巣の構造体(巣盤)を食べながら成長していきます。
やがて巣全体がボロボロになり、スズメバチたちは巣を放棄せざるを得なくなる場合もあります。
直接スズメバチを襲うのではなく、巣そのものをじわじわ内部から崩していくという攻撃スタイルは、まさに自然界のステルス系天敵とも言えるでしょう。
同属種でのスズメバチの天敵

スズメバチの天敵は、“別の生き物”だけではありません。
実はスズメバチ同士でも、縄張り争いやエサの奪い合いから壮絶な戦いを繰り広げることがあるのです。
ここでは「同じスズメバチ属」同士による、生存をかけたバトルをご紹介します。
同属種の巣を襲って幼虫を奪う “オオスズメバチ“

“スズメバチ界の王者”とも称されるオオスズメバチ。
体長は最大で4cmを超え、そのパワーと攻撃性は他のスズメバチを圧倒します。
実際、キイロスズメバチやコガタスズメバチの巣を集団で襲撃し、資源としてエサや幼虫を奪うために襲撃するのもよく見られます。
巣の中に侵入したオオスズメバチは、まず防衛の働きバチたちを倒し、幼虫やサナギを根こそぎ持ち去ってしまうため、襲われたスズメバチは壊滅してしまいます。
ただし、襲ったオオスズメバチ側も被害が無いわけではなく、戦いに参加した半数が敗れる事もあるなど高いリスクもあります。
ですが、スズメバチたちはほぼ同時期に栄養価の高いタンパク質源を求めて餌探しに必死になるので、同じ縄張り内のスズメバチを制圧して育ち盛りで栄養価の高い幼虫やサナギを狙うのは手っ取り早く合理的な方法でもあるのです。
キイロスズメバチの巣を乗っ取る “チャイロスズメバチ“

チャイロスズメバチは、その名のとおり全体的に茶色っぽい体色をしたスズメバチの一種です。
サイズは2cm~程度で、その行動パターンは他のスズメバチとはまったく異なり、キイロスズメバチやモンスズメバチの初期の巣を乗っ取るという驚きの戦略を持っています。
乗っ取りの方法は女王バチが単独でキイロスズメバチの巣に侵入し、もとの女王を倒して支配権を奪取します。
その後は残ったキイロスズメバチの働きバチたちをそのまま従わせ、合わせて自分の子どもたちを育てさせるという“完全なる支配構造”を築きます。
ただし、チャイロスズメバチは他のスズメバチと比べて特別強いというわけでもないので、侵入前に相手の巣のニオイを自分にまとい、匂いで同化しながら忍び込むという“スパイのような行動”を取ることも確認されています。
また、乗っ取りに失敗する場合もあり、その時は自分で営巣活動をします。
「力」でねじ伏せるオオスズメバチに対して、「知略」で支配するチャイロスズメバチ。
同じスズメバチでも、まったく異なる生存戦略を取っているのが本当に興味深いポイントですね。
哺乳類に分類されるスズメバチの天敵

最後にご紹介するのは、 “哺乳類”です。
意外にもスズメバチの巣を直接狙う大型動物が存在します。
ここでは野生の王者“クマ”と、意外な天敵“人間”をピックアップします。
サナギや幼虫を狙って巣ごと襲撃する “クマ”

スズメバチにとって、クマはまさに圧倒的な“物理”で襲い来る天敵です。
クマは木のうろや地中にあるスズメバチの巣を見つけると、ためらいもなく引きはがし、巣そのものを破壊して中の幼虫やサナギを根こそぎ食べてしまいます。
冬眠前に栄養をたっぷり蓄えたいクマにとって、スズメバチの巣は“高タンパクなプロテインバンク”のような存在です。
当然、スズメバチたちも集団で反撃しますが、クマの分厚い毛皮と皮膚にはほとんど効果がないとも言われており、多少刺されても気にせず捕食し続けます。
このようなクマの“黒くて大きい姿”は、スズメバチの本能にも強く刻まれています。
彼らはクマの黒い体毛を「天敵の象徴」として記憶しているため、同じように黒い服や髪の毛をした人間にも強く反応して攻撃を仕掛けることがある程です。
クマは、スズメバチの進化にすら影響を与えた“究極の天敵”ともいえる存在といえるでしょう。
ハチの子を好んで食べることもある“人間”

スズメバチにとって、もうひとつ無視できないのが“人間”という存在です。
私たちは彼らの巣を見つけては撤去し、時には「ハチの子」などを珍味としていただく文化もあります。
山間部を中心に、ハチの子が貴重なたんぱく源として重宝される地域もあり、スズメバチの巣を採取するのは“自然の恵み”として親しまれてきました。
しかし都市化が進み、人間とスズメバチが接触する機会が増えるにつれて、刺傷事故が社会問題化、今や“危険生物”としての印象が強まり、場所によっては積極的な駆除の対象となっています。
さらに「駆除」だけでなく「予防」という観点でもスズメバチの活動をコントロールしているのが現代の人間です。
自然界の天敵たちが“本能”でスズメバチと向き合うのに対し、人間は“知恵”や“道具”で対抗する存在と、スズメバチにとっては“最も厄介で高度な天敵”といえるでしょう。
天敵をスズメバチ駆除に使うのは現実的でない

ここまで、スズメバチに立ち向かう自然界の天敵たちを紹介してきましたが、実際にそれらの天敵を“人間の生活空間での駆除目的”で利用するのは、現実的とはいえません。
というのも、多くの天敵はあくまで「自然環境の中で偶発的にスズメバチを狙う存在」にすぎず、人間の都合に合わせてコントロールすることはほぼ不可能です。
たとえば、オオカマキリやオニヤンマを庭に放ったとしても、確実にスズメバチを退治してくれる保証はなく、かえって別の昆虫や環境への影響を及ぼすリスクも考えられます。
また、哺乳類や鳥類なども、例えばクマを呼んでスズメバチを駆除する…などというわけにはいかず、当然ながら現実味がありません。
こうした理由から、天敵はあくまで自然界のバランサーとしての役割にとどめ、人間の生活圏でスズメバチに対処するには、やはり別の方法を選ぶべきだといえるでしょう。
スズメバチを駆除する2つの手段

スズメバチは自然界で重要な役割を果たす一方で、私たちの生活圏に巣を作ってしまうと非常に危険な存在となります。
ここでは、スズメバチの駆除方法として、現実的な2つの選択肢をご紹介します。
自力で駆除する
比較的小さな巣や、まだ働きバチの数が少ない初期段階であれば、防護対策を講じたうえで市販のスプレーなどで自力での駆除を検討することも可能です。
その際には、以下のような点に十分注意する必要があります。
- 巣の位置を事前に確認し、日没後や夜間など、ハチの活動が鈍る時間帯に行動する
- 殺虫スプレーはスズメバチ専用のものを用意し、十分な射程距離があるかをチェック
- 全身を完全にガードする服装・防護具を用意する
- 必ず2人以上で行動し、万が一刺されたときの対応マニュアルを共有しておく
ただし、スズメバチは思っている以上に防御本能が強く、危険を感じたスズメバチがいきなり集団で襲いかかってきたり、しつこく追跡してくる危険性もあります。
「小さいから大丈夫だろう」「スプレーなら何とかなる」と安易に判断せず、少しでも不安がある場合は、すぐにプロの業者に依頼するのが安全です。
ハチ駆除専門業者に依頼する
スズメバチの巣がすでに大きくなっている場合や、人の生活動線に近い場所にある場合は、
自力での駆除は非常に危険です。
そんな時こそ頼れるのが、“ハチ駆除のプロフェッショナル”。
専門業者であれば、豊富な経験と専用装備、そして現場ごとの対応ノウハウを活かして、
安全かつ確実にスズメバチの巣を撤去・駆除してくれます。
特に以下のようなケースでは、迷わず専門業者に連絡するのが賢明です。
- 巣が高所や地中などにあり、位置がはっきり把握できない
- すでに威嚇飛行をしている
- アレルギー体質や高齢者・子ども・ペットが周囲にいる
- 自力での駆除に不安や恐怖がある
また、信頼できる業者であれば、駆除後の再発防止や予防アドバイスまで対応してくれることもあります。
ハチ駆除専門業者は“人間が持つ知恵と道具のすべて”を駆使した、スズメバチにとっての“最終天敵”と言える存在です。
無理をして命の危険を冒すよりも、プロに任せることが結果的に最も安心で確実な方法ですので安全な環境を守るためにも、「駆除は専門業者へ」が鉄則です。
ハチの駆除ならスズメバチ最強の天敵 ”ハチ駆除専門クリーンライフ”にお任せ
スズメバチに対して、自然界には数多くの天敵が存在します。
しかし本当に頼れるのは、豊富な実績と専門知識を持つ“人間のプロ”でしょう。
《ハチ駆除専門クリーンライフ》であれば全国対応・最短即日対応可能、専用の防護装備・薬剤・機材を使用し、どんな場所の巣でも迅速かつ安全に駆除します。
さらに、駆除後の再発防止対策や、巣を作らせないためのアドバイスも徹底サポート!駆除後も安心です。
少しでも危険を感じたら、ぜひハチ駆除専門クリーンライフにご連絡ください。
スズメバチに関してよくある質問
- 天敵がいるのに、なぜスズメバチの数は減らないのですか?
- スズメバチは非常に繁殖力が高く、防衛本能も強いため、多少の天敵がいても個体数が急激に減ることはありません。また、温暖化で生息地が拡大している種類もいます。
- スズメバチが家の近くに現れたらどうすればいいですか?
- 頻繁に出る場合は巣が近くにある可能性があります。見つけた場合は、無理に自分で駆除せず、早めに専門業者に相談することが安全です。
- 市販の殺虫剤でスズメバチは駆除できますか?
- 一部のスプレー型殺虫剤は効果がありますが、使用時は防護服が必要で、夜間に行うなどの安全対策が必須です。状況によっては業者に依頼する方がリスクを回避できるのでお勧めです。
危険ですので、無理せず
まずはプロに相談を!
- お支払い方法
-
- 現金払い

- 各種クレジットカード対応

- コンビニ後払い

- 銀行振込

- QR決済