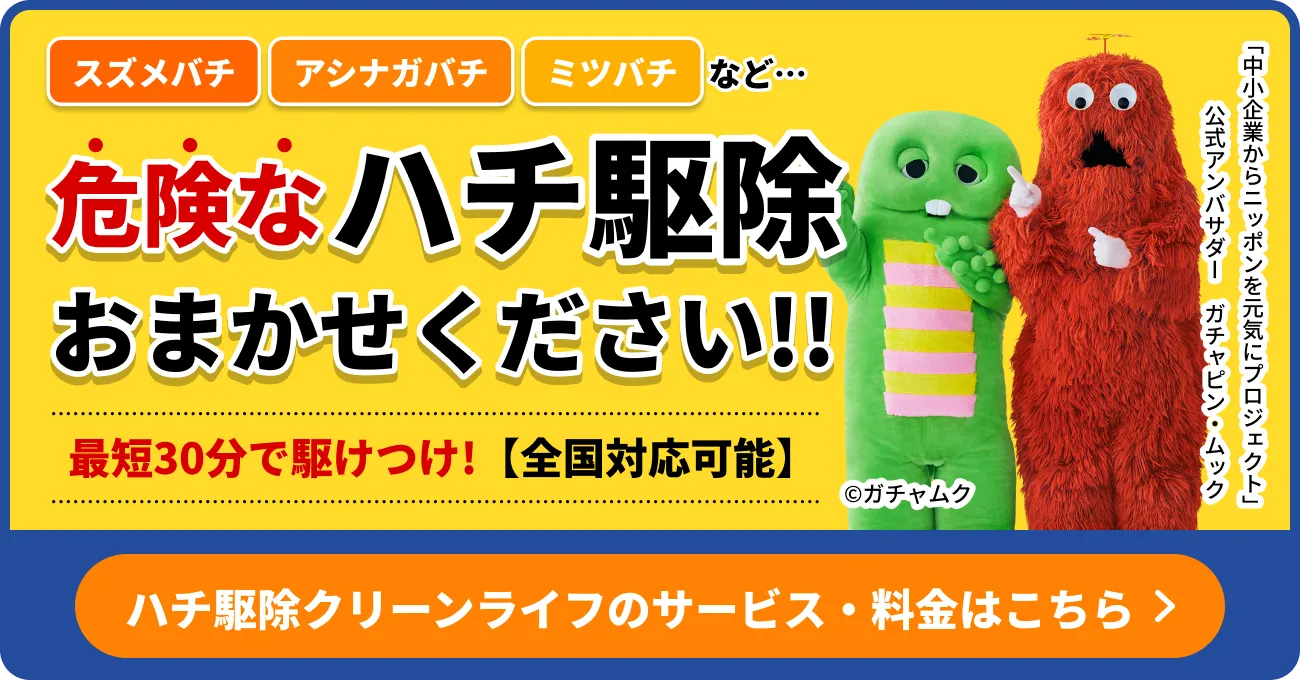- トップ
- スズメバチの巣はどこにある?身近な危険スポット・早期発見のポイントを徹底解説

スズメバチの巣はどこにある?身近な危険スポット・早期発見のポイントを徹底解説
スズメバチの巣を見落として、気づかないうちに近づいてしまうのは非常に危険です。スズメバチの巣に関して以下のようなお悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。
- 家の周りにスズメバチが飛んでいるが、どこに巣があるのか分からない
- 子どもやペットが庭で遊ぶので、危ない場所がないか不安
- 蜂の巣を見つけたが、種類が分からない
- 蜂の巣を早く見つける方法や、安全な対処方法を知りたい
本記事では、スズメバチが巣を作りやすい場所と、種類別の特徴、早期発見のポイントについて解説します。また、スズメバチに遭遇した時の対処法についても解説しているため、あわせて参考にしてください。
Contents
スズメバチが巣を作る場所4選

スズメバチは静かで風通しが良く、外敵に見つかりにくい場所を選んで巣を作ります。特に以下の4つのスポットは注意が必要です。
- 屋根の下・軒先
- 庭木・生け垣
- 倉庫・物置・ベランダ下
- 換気口・通気口・壁のすき間
人目につきにくい場所に巣ができていると、発見が遅れて被害が大きくなる恐れがあります。スズメバチが飛んでいるのを見かけたら、すぐにその周辺の環境を確認するようにしましょう。ここでは、上記4つのスポットについて詳しく解説します。
屋根の下・軒先
屋根の下や軒先は、スズメバチにとって好条件な場所です。なぜなら、風雨をしのげるうえに外敵から見えにくく、巣の素材となる木材の削りカスも豊富にあるためです。
初期の巣は小さく目立たないため、梅雨入り前の5月から6月にかけては特に注意してください。飛んでいる蜂を見かけたら、その行き先をよく観察してみてください。もしかすると巣の場所を突き止める手がかりになるかもしれません。特に日当たりの良い南側の軒下などは、頻繁にチェックしておくことをおすすめします。
庭木・生け垣
庭木や生け垣などの植物も、スズメバチが巣を作りやすいスポットです。葉の影に隠れるようにして巣が形成されるため、外からではなかなか確認しにくくなっています。
特に、剪定されていない木や、枝が密集している部分には注意が必要です。植木の裏や枝の間をよく観察することで、思わぬ場所で巣を発見する可能性があります。
ですから、蜂の飛来が多くなる時期には、庭に入る前に必ず目視で確認しましょう。
倉庫・物置・ベランダ下
普段あまり出入りしない倉庫や物置、そしてベランダ下の暗がりは、スズメバチにとって絶好の巣作りスポットです。特に長期間使用していない物置の中では、誰にも邪魔されることがないため、巣が大きく育ってしまうケースもあります。
出入りする機会がなくても、年に一度はこれらの場所を点検し、窓や扉を開ける際には内部に蜂が潜んでいないか慎重に確認しましょう。また、蜂が出入りする小さな穴や割れ目がないかもチェックしておくと安心です。
換気口・通気口・壁のすき間
換気口や通気口、そして外壁と屋根のすき間など、建物の構造上の隙間もスズメバチが入り込む絶好の場所です。特に壁の内部や天井裏に巣を作られてしまうと、外からはまったく見えず、蜂の出入りでしか気づけないこともあります。
巣の存在に気づかず放置すると、壁の中で巣が巨大化し、家屋に悪影響を与える可能性もあります。換気口の近くに蜂が頻繁に集まっているようなら、早急に駆除することをおすすめします。
【種類別】スズメバチが作る巣の特徴

スズメバチの巣は、種類によって形や場所、素材の使い方に明確な違いがあります。見た目が似ていても、蜂の性格や攻撃性、巣の成長速度なども異なるため、正しく種類を把握することが重要です。
ここでは、代表的な7種のスズメバチが作る巣の特徴について詳しく解説します。
オオスズメバチが作る巣の特徴
オオスズメバチの巣は、地中などの閉鎖的な空間に作られることが多く、外からはほとんど見えないのが特徴です。古いネズミ穴や枯れ木の根元などに潜んでおり、気づかずに近づくと突然刺されるリスクがあります。
オオスズメバチの詳しい巣の特徴や習性に関しては「オオスズメバチの特徴と危険性を徹底解説!適切な退治方法も紹介!」をご確認ください。
キイロスズメバチが作る巣の特徴
キイロスズメバチは、民家の軒先や天井裏、樹木の枝先などに大きなボール状の巣を作るのが特徴です。初期はテニスボールくらいの手のひらサイズですが、夏にはバスケットボール大に成長し、働き蜂の数も数百匹規模になります。
キイロスズメバチの巣の特徴や危険性に関してもっと詳しく知りたい方は「事故最多!都市部で最も危険なキイロスズメバチを解説」の記事をご覧ください。
モンスズメバチが作る巣の特徴
モンスズメバチの巣は、床下や物置の隅など、暗くて湿気の多い閉鎖空間に作られます。巣は釣り鐘状で底が抜けています。比較的地味な色合いであるため、なかなか気づけないかもしれません。
モンスズメバチはオオスズメバチほどではないものの、攻撃性が高いため、発見したら早めに駆除しましょう。
モンスズメバチの特徴や習性についてもっと詳しく知りたい方は「モンスズメバチの特徴や危険性を徹底解説!適切な退治方法も紹介!」の記事をご覧ください。
コガタスズメバチが作る巣の特徴
コガタスズメバチの巣は軒先や低い樹木、庭木の枝先など雨風を凌げながらも開放的な空間に作るのが特徴です。初期はとっくり型で、成長すると球状に変化します。
コガタスズメバチの巣の特徴や対処法について詳しく知りたい方は「コガタスズメバチの特徴と危険性について徹底解説!適切な退治方法も紹介!」の記事をご覧ください。
チャイロスズメバチが作る巣の特徴
巣が作られる場所としては軒下や屋根裏、外壁の隙間など比較的閉鎖した空間に多く、近年では都市部でも見かけられています。チャイロスズメバチは警戒心が強く、ほんの少しの刺激で攻撃的な行動を見せることもあるため、注意が必要です。
チャイロスズメバチの巣の特徴について詳しく知りたい方は「攻撃的で毒液噴射もするチャイロスズメバチの特徴と対策を徹底解説!」の記事をご覧ください。
クロスズメバチが作る巣の特徴
クロスズメバチは主に土の中や壁の隙間、落ち葉の下など目立たない場所に巣を作ります。形はボール状で、土の中にある場合は振動で巣を刺激してしまうと、クロスズメバチが飛び出してくるかもしれません。
クロスズメバチの巣の特徴についてもっと詳しく知りたい方は「クロスズメバチの生態や危険性を徹底解説!正しい対処法も紹介」をご覧ください。
ヒメスズメバチが作る巣の特徴
ヒメスズメバチの巣は、木の空洞や倒木、地中など人目につかない場所に作られます。巣の形は釣鐘型で、外皮にはまだら模様が見られることもあります。見つけにくい場所に作るため、山間部や森の中では特に注意が必要です。
ヒメスズメバチの巣の特徴についてもっと詳しく知りたい方は「危険性は低くても油断は禁物なヒメスズメバチについて徹底解説」をご覧ください。
スズメバチの巣が近くにあるサイン

スズメバチの巣は目につきにくい場所に作られることが多く、発見が遅れると被害につながります。しかし、巣が近くにある場合、下記のような前兆が見られます。
- スズメバチが同じ場所に何度も現れる
- 羽音が聞こえる
- 窓や網戸にぶつかってくる
これらのサインに早い段階で気づけば、早期退治も可能です。ここでは、スズメバチの巣が周囲に存在する可能性を示す代表的なサインについて詳しく解説します。
スズメバチが同じ場所に何度も現れる
スズメバチが毎日決まった場所に何度も飛来するようであれば、その周辺に巣がある可能性が高いと言われています。特に、庭木や軒先、ベランダの下などに同じ個体が現れる場合は、餌や巣材を運ぶために出入りしていると考えて良いでしょう。
働き蜂は一定の飛行ルートを保ちながら移動するため、通過する方向を観察することで巣の位置を推測できる場合もあります。スズメバチが何度も同じ場所に現れたら、周辺をよく見渡して巣がないか確認しましょう。
羽音が聞こえる
「ブンブン」という低く唸るような羽音が断続的に聞こえる場合は、巣がすぐ近くにある可能性が高いと言われています。静かな時間帯に壁の中や天井裏、軒下から聞こえる場合は、建物内部に巣を作られている危険性も否定できません。
羽音のボリュームが大きく、振動を感じるようなときには、すでに大きな巣が形成されていることもあるため注意してください。
窓や網戸にぶつかってくる
スズメバチが何度も窓や網戸にぶつかってくるようであれば、その近辺に巣がある可能性が高いと言われています。反射した自分の姿に反応している場合や、室内の光を目指して飛んでくることもありますが、何度も同じ場所に激突するようであれば、巣の出入口がその近くにあることを疑いましょう。
室内への侵入を防ぐために、窓やドアは開けたらその都度しっかり閉めておいてください。
スズメバチの死骸がある
敷地内やベランダ、玄関周辺でスズメバチの死骸を見つけた場合も、その近くに巣がある可能性が高いと言われています。なぜなら、スズメバチは巣の周囲で活動することが多く、寿命を迎えた個体や捕食者にやられた個体が巣の近くに落ちる傾向があるためです。
死骸を見つけた場合は、周辺の空間を注意深く観察し、蜂の出入り口や羽音の有無を確認してみましょう。
スズメバチが巣を作る時期と季節ごとの行動パターン

スズメバチの巣作りには明確な季節的傾向があり、時期ごとに行動パターンが大きく変わります。特に春から秋にかけては活動が活発化するため、予防や早期発見のためには季節に応じた注意が必要です。
ここでは、スズメバチの年間を通した主な動きと、それぞれの時期に気をつけたいポイントについて解説します。
春は女王蜂が巣作りを開始する季節
春は、冬眠から目覚めた女王蜂が巣作りを開始する季節です。3月下旬から4月ごろにかけて、静かな場所や雨風を避けられる軒先、屋根裏、木の根元などに小さな巣を作り始めます。
この段階では女王蜂が単独で活動しており、巣もまだ手のひらサイズほどです。早い段階で巣を見つけられれば、比較的安全に対処しやすいため、春は巣の兆候をチェックする重要な季節でもあります。
初夏〜夏は巣が急拡大するため最も注意が必要
5月から8月にかけて、巣は急激に拡大していきます。働き蜂が次々に羽化し、女王蜂は産卵に集中するため、巣から出てきません。
この時期の巣は、サッカーボール大からそれ以上の大きさにまで膨れ上がり、巣を守るために働き蜂の警戒心も強まるのが特徴です。人の出入りが多い庭や住宅の周囲で巣を作られると、接触の危険も高まるため、最も注意すべき季節です。
秋になると攻撃性が増加する
9月から10月にかけて、スズメバチは非常に攻撃的になります。これは働き蜂の数がピークに達し、巣の内部で新たな女王蜂や雄蜂が育てられるため、巣を守る本能が一段と強くなるためです。
また、餌の確保が難しくなる時期でもあるため、人が持つ食べ物や飲料にも引き寄せられやすい季節です。ですから、巣の近くに不用意に近づいたり刺激を与えたりしないよう、より慎重な対応が求められます。
冬は活動が減るものの古い巣が残っている
11月以降は気温の低下とともにスズメバチの活動が鈍り、12月にはほとんどの働き蜂が死に絶えます。ただし、古い巣がそのまま残っている場合、春に向けての再営巣場所と勘違いする人も少なくありません。
基本的にスズメバチは古い巣を再利用しませんが、場所としての条件が良ければ近くに再度巣を作ることがあります。ですから、冬の間に巣を撤去しておくことが、翌年の被害予防につながるのです。
スズメバチの巣にやってはいけない行動

スズメバチの巣を見つけた時、焦りや恐怖から下記のような誤った行動を取ってしまう人が少なくありません。
- 大声を出す
- 巣を棒でつつく
- 放置する
このような軽率な対応はかえってハチを刺激し、自分や周囲の人を危険にさらすおそれがあります。ここでは、これらの行動について詳しく解説します。
大声を出す
スズメバチは音や振動に敏感に反応します。そのため、巣の近くで驚いて大声を出すと、ハチが敵意を感じて攻撃してくる危険性があるのです。
特に、集団で活動している時期は、一匹が警戒すると周囲の働き蜂も一斉に攻撃態勢に入るため非常に危険です。巣の存在に気づいたら、静かにその場を離れましょう。
巣を棒でつつく
「どれくらい大きいか見てみたい」、「中にハチがいるのか確認したい」といった軽い気持ちで、棒などで巣をつつくのは危険な行為です。刺激を受けたスズメバチは一斉に飛び出し、集団での攻撃を仕掛けてきます。
スズメバチにとって巣は命をかけて守る場所であるため、巣に直接手を出すのは絶対に避けてください。
放置する
巣を見つけても「そのうちいなくなるだろう」と放置してはいけません。巣を放置した結果、巣が人の生活圏にまで影響を及ぼし、刺傷事故が発生するケースも少なくありません。
被害が出る前に、駆除することをおすすめします。
スズメバチの巣を放置してはいけない理由

ではなぜ、スズメバチの巣をそのままにしておいてはいけないのでしょうか。その理由は以下の3つです。
- 命の危険に晒される可能性があるため
- 巣の成長とともにハチの数が増えるため
- 近隣トラブルに発展する可能性があるため
巣の規模が拡大すれば攻撃のリスクが高まり、周囲の人を危険に巻き込む可能性もあります。ここでは、スズメバチの巣を放置してはいけない理由について詳しく解説します。
命の危険に晒される可能性があるため
スズメバチの毒は強力で、刺されると激しい痛みや腫れ、アレルギー反応などが生じることがあります。特にアナフィラキシーショックを起こすと、最悪の場合は命を落とす危険性もあるのです。
このように、たった1匹の攻撃でも深刻な被害につながるため、巣がある環境では常に生命の危険と隣り合わせであることを意識してください。
巣の成長とともにハチの数が増えるため
放置されたスズメバチの巣は、1ヶ月もしないうちに数倍の大きさに膨れ上がります。巣が拡大することで働き蜂の数も急増し、攻撃性が高まると人が近づくだけで攻撃対象になる可能性が出てきます。
初期の小さい巣なら比較的安全に撤去できる場合もありますが、放置すると手がつけられなくなるため、早期対応が重要です。
近隣トラブルに発展する可能性があるため
スズメバチの巣が住宅地にある場合、自分だけでなく近隣住民も刺されるリスクが高くなるため注意が必要です。通学路や公園、駐車場など人通りの多い場所に近い場合は、知らぬ間に他人に被害を与えてしまうことも考えられます。
被害が発生すれば責任問題に発展する可能性もあるため、早めに対処しましょう。
スズメバチの巣を見つけた時の対処法

スズメバチの巣を発見した際には、慌てずに冷静な判断が求められます。主な対処法は以下の2つです。
- 自力で退治する
- 蜂駆除専門業者に依頼する
状況や危険度に応じて、最適な対処法を選びましょう。ここでは、これら2つの対処法について詳しく解説します。
自力で退治する
小さな巣であれば、市販の殺虫スプレーなどを使用して自力で退治することも可能ですが、細心の注意が必要です。夜間や早朝などハチの動きが鈍い時間帯を選び、防護服を着用して作業を進めなければなりません。
また、刺されるリスクや、うまく駆除できなかった場合の再攻撃といった危険も伴うため、少しでも不安を感じたら作業を中断してください。
もし、自力での退治を検討している人は以下の記事を参考にしてください。この記事では具体的な退治の手順や安全に進めるポイントを解説しています。
スズメバチを駆除したい時はどうしたら良い?自力での退治方法とおすすめ駆除方法を紹介!
蜂駆除専門業者に依頼する
スズメバチの巣が大きい場合や、人通りの多い場所にある場合は、蜂駆除専門業者に依頼するのがおすすめです。プロの駆除業者は適切な装備と薬剤を使用して、短時間で巣を除去してくれます。
『ハチ駆除専門クリーンライフ』ではエリア対応が広範囲である上、最短即日対応、追加料金なしといった明確なサービスで利用者からご好評をいただいております。放置してリスクが高まる前に一度ご相談ください。
スズメバチの巣を見つけたらハチ駆除専門クリーンライフにご連絡を!

スズメバチの巣を発見した際は、決して自己判断で近づかず、速やかにプロに相談することが大切です。スズメバチは刺激に敏感で、巣を守るために集団で襲いかかる習性があります。
なかでも、住宅地や人通りの多い場所では、わずかな刺激が大きな事故につながりかねません。
『ハチ駆除専門クリーンライフ』では、全国対応・最短即日駆除・明確な料金体系で、安心かつ迅速にスズメバチの巣を撤去いたします。無料相談や見積もりも可能なため、まずはお気軽にご相談ください。
大切な家族やご近所を守る第一歩として、プロによる安全な対応を選びましょう。
スズメバチの巣に関してよくある質問
- スズメバチの巣はどれくらいの大きさですか?
- 初期はテニスボールほどですが、夏にはバレーボール以上になることもあります。短期間で急激に大きくなるため、早期発見が非常に重要です。
- スズメバチの巣が空なら放置していても問題ないですか?
- 古い巣にハチが戻ることは基本的にありませんが、同じ場所に新たな巣が作られることがあります。安全のためにも撤去しておくのが賢明です。
- 自宅の敷地外で巣を見つけたらどうしたらいいですか?
- 公共施設や電柱などに巣がある場合は、自治体や管理機関に連絡しましょう。個人で駆除をおこなうと、法的なトラブルに発展する可能性があります。
- スズメバチの巣を自力で退治しても問題ないですか?
- 防護服や専用の薬剤を使えば不可能ではありませんが、刺される危険や駆除の失敗が大きなリスクとなります。そのため、専門業者への依頼する方法が最も安全です。
- 蜂駆除業者の選び方を教えてください
- 駆除実績、対応地域、料金の明確さ、即日対応の可否、アフターケアの有無を確認するのがポイントです。
危険ですので、無理せず
まずはプロに相談を!
- お支払い方法
-
- 現金払い

- 各種クレジットカード対応

- コンビニ後払い

- 銀行振込

- QR決済