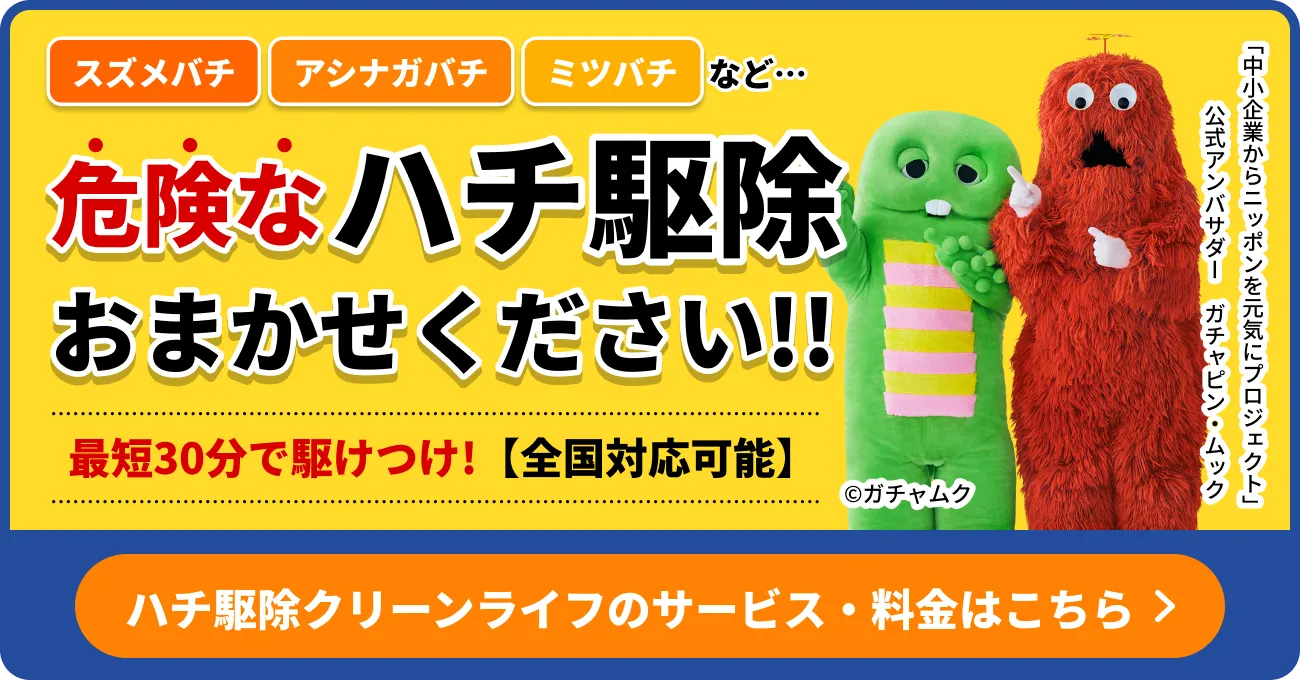- トップ
- 日本に生息するスズメバチの種類とその特徴を解説

日本に生息するスズメバチの種類とその特徴を解説
私たちの生活圏で遭遇する可能性が高い9種類のスズメバチにフォーカスし、特徴や見分け方、生息地などをわかりやすく解説します。
種類別に知っておくことで、万が一の遭遇時にも冷静に対応しやすくなります。ぜひチェックしてみてください。
Contents
日本に生息する危険なスズメバチは主に9種類

日本には、スズメバチ属が8種、クロスズメバチ属が5種、ホオナガスズメバチ属が4種の、あわせて3属17種のスズメバチが生息しています。
ただし、それぞれの種類によって分布地域や性質は大きく異なり、全国どこでも見かけるというわけではありません。
本記事では、その中でも私たちの身近で遭遇しやすい危険性の高い9種類に絞って紹介していきます。
| 特に危険なスズメバチ | 特徴やポイント |
|---|---|
| オオスズメバチ | 最大級の体と最強の毒性 |
| キイロスズメバチ | 被害件数No.1の獰猛な性格 |
| チャイロスズメバチ | 生息地拡大中・毒液噴射も |
| コガタスズメバチ | 比較的温厚・住宅地に多い |
| ツマアカスズメバチ | 外来種・高所に巨大な巣 |
| ツマグロスズメバチ | 沖縄に多くツートンカラーが特徴 |
| モンスズメバチ | 夜も活動・波打つ縞模様 |
| ヒメスズメバチ | 毒量が多く巣は意外に小さい |
| クロスズメバチ | 小型・毒性弱めだが土の中に大きな巣 |
巨大で凶暴、最も危険なオオスズメバチ

日本国内で最も危険なスズメバチとして知られるのが、このオオスズメバチです。
驚異的な体の大きさに加え、攻撃性・毒性ともに最強クラス。
自然の多い地域で遭遇することが多く、刺された場合のリスクは非常に高いため、見かけた際には決して近づかず距離を取ることが鉄則です。
ここでは、その恐るべき特徴を詳しく解説していきます。
攻撃性と毒性が非常に強い
オオスズメバチはスズメバチの中でも最も凶暴で、攻撃性と毒性の両方が非常に強いのが特徴です。
その巣も大きく、夏の繁殖期などは80cmを超え、コロニーの個体数も1000匹を超えることがあります。
また巣を刺激すると一斉に襲ってくるため、刺された際のダメージも大きく、毎年のように重傷者や死亡例が報告されるほど危険です。
なお、オオスズメバチの行動範囲は巣から半径1~2km程ですが、複数匹見かけた場合は近くに巣がある可能性があります。ハイキングなどでは十分に注意してください。
また巣を見つけた場合は刺激を与えず、巣の近くには絶対に近づかないようにしましょう。
3~4cm越えの巨大な体に黒と黄色の模様
オオスズメバチの体長は女王バチで5cm以上、働きバチも3~4cm程度と大人の親指ほどの大きさがあり、見た目だけでも迫力があります。
堅い外骨格と強靱な顎、太く長い毒針を持っており、大きく目立つオレンジ色の頭部と、黒い胸部、腹部に黒とオレンジ色の縞模様が入っているのが特徴です。
また、近づきすぎた場合、攻撃前の威嚇としてその大きな顎をカチカチと鳴らして威嚇音を発することがあります。
この音が聞こえたら大きな声を出したり手で振り払うなどは絶対にせず、静かにその場を離れるようにしましょう。
山林や地中に巣を作る傾向がある
オオスズメバチは山間部や森林など、自然の多い場所に巣を作る傾向がありますが、民家の屋根裏や床下にも作ることがあるため油断は禁物です。
警戒心が強く警戒範囲も巣から10mと広いので、特に地面に空いた穴や、木の根元の空洞などの巣を見落としやすく、不意に近づいて襲われてしまうケースも多発しています。
ハイキングや山歩きの際は注意が必要です。
オオスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
被害最多!獰猛で攻撃性の高いキイロスズメバチ

スズメバチの中でも人とのトラブルが最も多いのがキイロスズメバチです。
都市部にも適応しており、私たちの生活圏で最も遭遇しやすい存在といえます。(参考:九州大学大学院 農学研究院)
その俊敏さと攻撃性の高さはトップクラスで、刺激を与えると集団で一斉に襲いかかってくることも。
被害件数が多い理由やその危険性を、詳しく見ていきましょう。
人との遭遇率が高く被害件数が最も多い
キイロスズメバチは屋根裏やベランダの軒下、室外機の中など、人の暮らしに近い場所に巣を作るため遭遇率が大変高く、毎年の刺傷事故数でも最多クラスです。
キイロスズメバチは巣の規模も大きく、放っておくと80cmを超え700~1000 匹のコロニーとなることもあります。
また大変攻撃的で警戒心が高く、警戒範囲も巣から約10mと広いので気がつかないうちに足を踏み入れてしまう可能性があります。
さらに攻撃態勢に入ったあとは多数の働きバチが一斉に襲いかかり、しつこく30m近くも追跡してくるため、住宅街では特に早めの対処が重要です。
2.5cm程度とスズメバチの中では小柄
キイロスズメバチの体長は、女王蜂で2.5cm程度、働きバチだと1.7〜2.4cm程度と、オオスズメバチなどと比べるとやや小柄です。
しかし、小さな体に見合わないほどの攻撃性と機動力を持つため油断は禁物です。
全体的にオレンジ~黄色味が強く、全身に産毛が生えているのが特徴で、比較的、見た目で判別しやすい種類のひとつでもあります。
都市部に巣を作り引っ越しする習性がある
住宅地の屋根裏や軒下、エアコンの室外機の中など、人の生活圏内に巣を作ることが多いのもこの種類の特徴です。
初期の巣は閉鎖的な空間に作ることが多いですが、ある程度育つと巣の移転をする習性を持っており、軒下や看板の裏など開放的な場所に巣営します。
引越し後は特に巣が大きくなる速度が速く、気がついたら身近な場所に巨大な巣ができていた、ということも少なくありません。
キイロスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
生息地拡大で遭遇率が高まるチャイロスズメバチ

チャイロスズメバチは、もともと北海道や東北地方などの寒冷地を中心に生息していた種類ですが、近年は本州各地にも分布を広げている要注意のスズメバチです。
「キイロスズメバチ」や「モンスズメバチ」に巣を乗っ取るという珍しい習性も持っています。
遭遇率は低いスズメバチですが、大変獰猛なためしっかり把握しておきましょう。
攻撃的で上空から毒液も飛ばしてくる
チャイロスズメバチは、オオスズメバチに次ぐ獰猛さで知られており、大変攻撃的なのが特徴です。
わずかな刺激でも即座に集団で反応し、周囲に脅威を与えます。
また、チャイロスズメバチの毒針は、他のスズメバチよりも太く長いのも特徴の一つで、その毒は痛みを引き起こす成分濃度が高く、刺された際の痛みはオオスズメバチ以上に感じることもあるようです。
また、飛行しながら毒液を噴射してくる性質があり、目に入ってしまうと視覚障害や激しい角膜炎を引き起こすことがあります。
警戒範囲は巣から約3m程度と前述したオオスズメバチやキイロスズメバチよりは狭いものの、近づくだけでためらいなく襲ってくるので危険です。
2cmほどの大きさで光沢のある赤褐色が特徴的
チャイロスズメバチの体長はおおよそ2cm程度と、スズメバチの中では中型クラスですが、全身赤みがかった褐色で、ツヤのある質感が特徴です。
外骨格は大変硬く鎧のようで、オオスズメバチの毒針が刺さらない事もあるほど強靱です。
す。
スズメバチの中では比較的識別しやすい特徴を持っていますが、見慣れていない人にとってはスズメバチの仲間とは気づきにくく、危険性を認識できないまま近づいてしまうおそれがあります。
あらかじめ特徴を知っておくことが、自身を守ることにもつながります。
寒冷地から本州へも生息地が拡大している
チャイロスズメバチは、北海道や東北の一部など、寒冷な地域にのみ生息していた準絶滅危惧種として指定されている希少なスズメバチです。
しかし近年では、地球温暖化や都市環境の変化への適応が進み、本州中部や関東地域でも確認されるようになってきました。
なお、絶滅危惧種とはいえ、生活圏に巣を作った場合は刺傷被害のリスクが高くなるため、駆除を検討する必要があります。
その際は、専門業者に相談しながら対応方法を判断することが重要です。
環境保全と安全確保のバランスをとることが求められます。
チャイロスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
迫力ある大きさで身近に生息するコガタスズメバチ

コガタスズメバチはその名前とは裏腹に、決して“小型”とは言えないサイズ感を持つ、存在感たっぷりの中~大型に属するスズメバチです。
比較的おだやかな性格ではありますが、住宅地でもよく見かける種類であり、知らずに近づくと攻撃されるリスクもあるため注意が必要です。
比較的温厚だが住宅地で遭遇しやすい
コガタスズメバチは攻撃性がそれほど高くないとされ、巣を強く刺激しない限り、すぐに攻撃してくるケースは少ない種類です。
その一方で、民家の庭や軒先、公園など人の生活圏で巣を作ることが多いため、遭遇率が高いのが特徴でもあります。
性格が穏やかと言っても、巣を刺激されたり身に危険を感じたりすれば集団で攻撃してきます。
身体が大きいので刺されたときの毒の量も多く危険です。
なお、コガタスズメバチの警戒範囲は巣から1~2m程度と言われており、もし巣を見つけた場合も刺激せずに静かに離れるようにしましょう。
オオスズメバチより小さいだけで小型ではない
コガタスズメバチの体長は約2.5〜3cmほどとされ、オオスズメバチと比べれば小さいだけで、決して小型ではなく一般的なスズメバチよりは大きくて迫力のある体格です。
顔はオレンジ色、胴体が黒、腹部はオレンジ色と黒色の太い縞模様と、オオスズメバチとよく似た見た目をしていますが、オオスズメバチと違って3cmを超えることはまずありません。
また、オオスズメバチは身体に対して顔が大きいですが、コガタスズメバチは小顔で目が大きく、かわいい顔つきに見えます。
個体差もありますがオオスズメバチをコガタスズメバチと勘違いして油断することが無いよう、ぜひこれらの特徴を把握しておいてください。
木の枝や軒下など開放的な空間に巣を作る
初期の巣はトックリを逆さにしたような形で下に入り口があり、女王蜂は一匹で素作りをしています。
初夏以降、働きバチが動き出すとマーブル模様の球体になり最大30cm程度まで大きくなりますが、全盛期でも群れの個体数は150匹程度と比較的小規模なコロニーでもあります。
巣は木の枝や軒下など、開放的な空間に作られますが、高さ2〜3mの位置に作られることが多いため、見上げるだけでは気づきにくいことも多いでしょう。
家庭菜園や洗濯物干しの際など、ふとした日常動作で接近してしまうことがあるので注意が必要です。
コガタスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
遭遇率は低いが超攻撃的なツマアカスズメバチ(外来種)

ツマアカスズメバチは、ともと中国南部、台湾、東南アジア等に生息していましたが、2012年頃に対馬市に侵入していることが確認された外来種のスズメバチです。
なお、韓国でも2003年に釜山でツマアカスズメバチが初めて確認されて以来爆増しており、対馬に侵入したツマアカスズメバチをDNA解析した結果、中国産で韓国を起源とする種であることが判明しています。
このようにツマアカスズメバチは、山間部に限らず都市部でも生息できるなど適応能力も高く、最近では九州や山口県で確認されるなど日本でも侵入が拡大しています。
ハエなど飛翔昆虫を好んで食べるのですが、ニホンミツバチも捕食するため養蜂への影響件されており、定着すれば生態系への影響も非常に大きいとされています。
なお、人との遭遇率はまだそこまで高くないものの、一度攻撃態勢に入ると追跡距離・攻撃性ともにトップクラスの危険なスズメバチです。
その執念深さと繁殖力、適応力の高さから、“最も警戒すべきスズメバチ”との声も上がっています。
攻撃的だが活動期の遭遇率は低い
現時点では主に九州や対馬などで確認されており、全国的には遭遇率の低いツマアカスズメバチですが、その恐ろしさは、その尋常ではないしつこさにあります。
警戒範囲は約10m、攻撃態勢に入ると最大40m以上も人を追いかけてくるなど、キイロやオオスズメバチを上回る“執念型”の危険なスズメバチです。
スズメバチの飛行速度は、種類にもよりますが時速30~40km程度と言われているので、人間が刺されずに走って逃げ切れるのはまず不可能でしょう。
今後の拡大が懸念されている外来生物ですので、見かけたら近づかず、自治体や専門機関に速やかに連絡することが推奨されています。
腹部の先のみが赤褐色で他は黒い
ツマアカスズメバチは名前の通り、腹部の先端部分のみが赤褐色になっているのが最大の特徴です。
脚先が黄色くアゴの周りがオレンジ色ですが、それ以外の体色は全体的に黒く、遠目ではアシナガバチや他の黒系のハチと見分けがつきにくいこともあります。
体長は2〜3cmほどと中型ですが、羽音が大きく飛行スピードも速いため、遭遇時の威圧感はかなりのものです。
高所に巨大な巣を作る
ツマアカスズメバチは、高所や木の上など人の目につきにくい場所に巣を作る傾向があります。
球形の大型の巣を好み、最大で1mに達することもあるなどかなりの大型です。
そこに生息する蜂の数もおおよそ3,000匹から3万匹と、在来種のスズメバチとは比較にならないほど多く、さらに秋に誕生する新しい女王バチの数は3,000匹から1万匹に上るとも言われており、繁殖力も非常に高いスズメバチです。
遭遇率はまだそこまで高くないですが、警戒範囲も巣から10mと広いため注意が必要です。
ツマアカスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
旅先での遭遇に注意!ツマグロスズメバチ

ツマグロスズメバチは、主に沖縄などの南西諸島に生息するスズメバチで、普段馴染みがなくても旅行先などで遭遇する可能性があるため注意が必要です。
毒性はそこまで高くないですが、警戒心が強く攻撃的です。
特徴を把握して遭遇時の対処方法を確認しておきましょう。
巣に近づくとしつこく攻撃される
他のスズメバチと同様、ツマグロスズメバチも巣に近づきすぎると攻撃されます。
警戒範囲は巣から10mと広めですが追跡距離は10m程度と、他の警戒心が高めのスズメバチに比べればあっさり引き返すイメージです。
なお、最盛期には100~800匹の働きバチが巣を守っていることもある大所帯なので、巣が攻撃されたと認識されれば即働きバチが飛び出してきて一斉に襲われてしまいます。
絶対に巣に近づくのは止めましょう。
腹部が黄色で先端が黒のツートンカラー
女王蜂の体長は2.5~3cmほどですが働きバチは2cm前後と中型サイズのスズメバチです。
頭と胴体は明るめの褐色ですが、腹部が鮮やかなレモン色と先端だけが黒くなる“ツートンカラー”が大きな特徴です。
見た目の特徴がはっきりしているので他のスズメバチとの見分けも簡単な種類といえるでしょう。
沖縄に生息し設置場所で巣の形が変わる
ツマグロスズメバチの巣は、初期は地上から1m程度の高さに女王蜂が単独で作り、トックリを逆さにしたような形で出入り口は下に設置されています。
その後、働きバチが羽化してくると巣も大きくなり球状や楕円形へと育っていきます。
また、このタイミングでさらに高所へ引っ越すこともありますが、台風が多い沖縄の気候上、雨風をしのげる軒下などにも巣営するなど、様々なパターンがあるようです。
ツマグロスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
暗くても活動できる危険なモンスズメバチ

モンスズメバチは、女王蜂が3cm程度、働きバチは2~2.7cm程度の中型のスズメバチです。
日本では北海道~九州の平野部や山間部など全国に広く見かけるハチですが、ヨーロッパでも幅広く生息しています。
なお、ヨーロッパでは「3箇所刺されると死ぬ」という迷信が拡がり徹底的に駆除された結果、絶滅危惧種に指定されている地域もあります。
攻撃性が高く夜も活動する
モンスズメバチの最大の特徴は、日没後の暗い時間帯でも飛び回ることがあるという点です。
モンスズメバチの目は他のスズメバチとは異なる構造をしており、夜間でも少ない光量で光を感知することが可能です。
また、身体に脂肪分を多く蓄えており、気温が下がる夜間でも活動が可能となっています。
ライバルとなる同種や鳥類といった天敵が少ない夜間に活動できることは、生存戦略としてとても有効な進化といえるでしょう。
なお、照明や懐中電灯に反応して寄ってくることもあり、夜間の屋外作業中に突然襲われるケースも報告されていますので人間も注意が必要です。
黄色と黒の縞模様が波打って見える
モンスズメバチは中型のスズメバチで、見た目はコガタスズメバチやキイロスズメバチに似ており、キイロスズメバチと同様に腹部の先端が黄色になっています。
腹部が黄色と黒の縞模様が波打つように見えるのが特徴なので、この部分でモンスズメバチなのかを判別可能です。
なお生息数が少ないため被害件数も少なめですが、キイロスズメバチに次いで攻撃性が高いとされており、遭遇時は注意が必要です。
木のウロに巣を作り下部の穴が入口
モンスズメバチは木のウロなど閉鎖的な場所に巣を作りますが、天井裏など人間の生活圏内にも巣営するので注意が必要です。
また、巣の下部が開放されており、下から見ると巣盤が丸見えなのもモンスズメバチの特徴です。
なお、巣が大きくなってくると引越しを行う修正もあり、この点はキイロスズメバチとも共通しています。
モンスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
巨大で毒量が多く危険なヒメスズメバチ

ヒメスズメバチは、その威圧的な体格と、非常に多い毒量で知られる大型のスズメバチです。
性格は比較的穏やかで遭遇率も高ないため全国的に被害件数も低いですが、刺されたときのリスクを考えると、最も警戒すべき種類のひとつです。
比較的穏やかだが毒の量が多い
ヒメスズメバチは他の攻撃的なスズメバチと違い、自ら積極的に攻撃してくることは少ないとされています。
ただし、体が大きい分、1回の刺傷で注入される毒の量が非常に多く、人によっては強い痛みや腫れ、アナフィラキシーショックを引き起こすこともあるため注意が必要です。
「刺激しなければ大丈夫」と油断せず、見かけたら距離をとることを心がけましょう。
国内トップクラスの大きさでお尻の先が黒い
ヒメスズメバチの体長は女王バチで4cmを超えることもあるほど巨大で、オオスズメバチと並ぶ圧巻の存在感があります。
見た目の特徴は、黒っぽい頭部と胸部、そして腹部のオレンジがかった縞模様があります。
最大のポイントは、腹部の先端が黒くなっていることで、これが他のスズメバチと見分ける際の決め手となります。
巣は大きくなっても10cm程度と小さい
驚くべきことに、これだけ巨大な体格を持つにもかかわらず、巣の大きさは最大でも直径10cmほどとかなり小規模です。
また、成虫した働きバチの数も多くて80~100程度と少ないのも特徴です。
なお、主に土の中や木の根元の空洞など、目につきにくい場所に巣を作るため、気づかずに近づいてしまうケースが少なくありません。
住宅地よりは森林や雑木林での遭遇が多いため、登山や山歩きの際には注意が必要な種類です。
ヒメスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
蜂の子を食べる地域もあるクロスズメバチ

クロスズメバチは、スズメバチの中でも最も小型で、比較的穏やかな性質を持つ種類です。
攻撃性・毒性ともに弱めで、基本的には人を襲うことはありません。
一部地域では「ヘボ」「ジバチ」などの名で親しまれ、蜂の子が食材として重宝されていることもある、ちょっと異色な存在です。
ただし、巣を刺激すれば刺される危険性はあるため、注意は必要です。
攻撃性・毒性がともに低い
クロスズメバチは他の大型スズメバチに比べてかなりおとなしい性格で、巣を刺激しない限り積極的に攻撃してくることはほとんどありません。
また、毒性も非常に弱く、刺されても症状が軽いことが多いですが、体質によってはアレルギー反応が出る可能性もあるため油断は禁物です。
1㎝程度と小さく胴体は黒に細い白線が入っている
体長はわずか1cm程度とスズメバチの中で最小クラスなため、アブやハエと間違われることも良くあります。
全体的に黒っぽい体色で、胴体に細く入った白い線模様が特徴です。
見た目も “スズメバチ”という印象から離れているので気づかず近づいてしまうこともありますが、小さくても集団でいると巣を守ろうとするため、注意が必要です。
土の中に巨大な巣を作る
最大の注意点は、クロスズメバチは地中に巨大な巣を作るということです。
直径50cmを超えることもあり、庭の隅や畑の土の中にひっそりと作られている場合があります。
地中に巣を作るので、外からは巣の規模感がわかりにくく、またピーク時は1000〜3000匹もの成虫がいることもあるので、うっかり刺激してしまわないようにクロスズメバチが数匹飛んでいるときはその行方をしっかり観察してみると良いでしょう。
クロスズメバチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください!
さらに細かい分類のスズメバチも存在する

ここまで紹介してきた9種類のほかにも、自然界には珍しいスズメバチたちが存在します。
遭遇する可能性は低いものの、独自の特徴や生態を持った種も多く、知っておくことでさらに興味深くスズメバチの世界を理解できます。
以下では、あまり知られていないスズメバチ3種+特定外来生物を簡単にご紹介します。
■ 太陽光発電するオリエントスズメバチ
太陽光をエネルギー源にするという驚きの特性を持つスズメバチです。
頭部の赤茶色と、腹部の鮮やかな黄色い帯がありモンスズメバチと見た目がよく似ています。
また80%という高濃度のエタノールをカロリー摂取の目的で飲み代謝できるなど他にはない特性を持っています。
■ キオビホオナガスズメバチは小型で攻撃的
北海道と本州に生息している働きバチの成虫で1.4~1.6cm程度の小型のスズメバチです。
一見クロスズメバチと似ていますが、ホオナガスズメバチ属に属しており、ホオナガスズメバチ属の中では一番攻撃性が高く注意が必要です。
■ 要注意の外来生物“ナンヨウチビアシナガバチ”、” チャイロネッタイスズバチ”
ともに本来は南方系の種で、外来生物として日本国内でも発見されている要注意種です。
体は小さめで、アシナガバチに似ていますが、行動範囲が広く定着すると生態系への影響が心配されています。
スズメバチの駆除方法

スズメバチを見つけた場合、状況によっては早急な駆除対応が必要です。
刺傷事故を防ぐためにも、以下の方法を参考に安全に対処しましょう。
殺虫スプレーなどで自力で対応する
市販のスズメバチ専用殺虫スプレーを使えば、自力で駆除することも可能です。
ただし、巣が大きい場合や、高所や手が届かない狭い場所などの場合は非常に危険ですので無理に自力で対処するのは避けましょう。
なお、自力で対処するときに特に注意すべきポイントは以下です。
- 作業は必ず早朝か夕方の活動が少ない時間帯に行う
- 長袖・厚手の服・防護ネットを着用する
- スプレーは風上から、1m以上の距離を保って使用する
- 1回で駆除しきれなければ無理せず撤退する
より詳しくスズメバチの駆除方法を知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
スズメバチを駆除したい時はどうしたら良い?自力での退治方法とおすすめ駆除方法を紹介!
ただし、自力での対応には限界があるため、次に紹介する業者依頼がおすすめの手段です。
蜂駆除専門の業者に依頼する
「巣の場所が分からない」「蜂の巣が高所にある」「活動が活発」そんなときは、専門業者への依頼が最も安全かつ確実です。
プロの業者は、専用の防護服や器具を使って安全に駆除してくれるだけでなく、再発防止のアドバイスや予防施工も行ってくれます。
小さなお子様やペットがいる家庭、高齢者が同居している家庭では、リスク回避のためにも専門家の対応がおすすめです。
危険なスズメバチの駆除ならハチ駆除専門クリーンライフにお任せ
スズメバチの巣を見つけたら、まずは慌てず、信頼できる業者に相談することが重要です。
ハチ駆除専門クリーンライフでは、経験豊富なスタッフが迅速・丁寧に対応。
全国対応可能で、見積もり無料&即日対応も可能です。
- 自宅の庭木や軒下に巣を発見した
- ベランダや外壁近くでスズメバチが飛んでいる
- 小さな子どもやペットがいるので自力で駆除するのが不安
こんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。安全と安心のために、専門のプロが全力でサポートいたします。
スズメバチに関してよくある質問
- 危険なスズメバチとそうでないスズメバチの見分け方はありますか?
- 見た目の違いはありますが、素人が判別するのは非常に難しいのは実情です。近づいたり刺激したりせずに、巣の有無や個体数などの状況から判断するのが安全です。
- 家の近くで見かけたスズメバチはすぐ駆除した方がいいですか?
- スズメバチの行動範囲は、一般的に巣から半径1~2km程度と言われており、1匹だけなら偶然の可能性もありますが、頻繁に飛んでいる・軒下などを出入りしている場合は巣がある可能性大です。すぐに専門業者に相談しましょう。
- 自分でスズメバチの巣を駆除してもいいですか?
- 基本的にはおすすめできません。特にオオスズメバチやキイロスズメバチの巣は攻撃性が高く、防護服・夜間作業・飛来数の把握など専門知識が必要です。安全のため業者依頼が安心です。
- スズメバチの巣がないのに飛んでくることはありますか?
- はい、水やエサを探して飛んでくるケースがあります。特に初夏〜秋は活動が活発で、ジュースの甘い匂いにも寄ってくるので、キャンプなどでは特に注意が必要です。
危険ですので、無理せず
まずはプロに相談を!
- お支払い方法
-
- 現金払い

- 各種クレジットカード対応

- コンビニ後払い

- 銀行振込

- QR決済