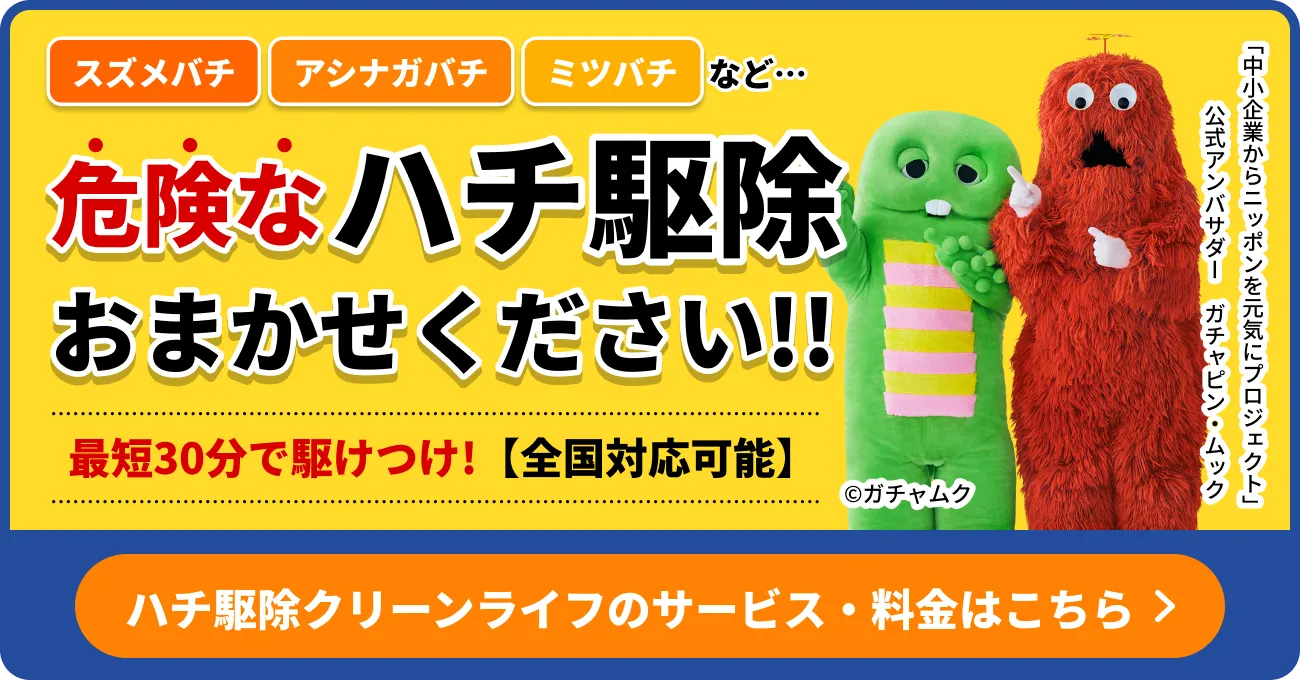- トップ
- スズメバチの生態を徹底解説!習性や危険性を知って身を守ろう

スズメバチの生態を徹底解説!習性や危険性を知って身を守ろう
夏になると姿を見せるスズメバチ。名前を聞くだけで恐ろしい印象を持つ方も多いでしょう。
本記事では、スズメバチの生態を詳しく解説します。
- 「いつ頃活発に動くの?」
- 「刺されたら命に関わるって本当?」
- 「巣を見つけたらどうすべき?」
上記のような疑問に向けて、攻撃性のある生態や行動パターン、スズメバチに遭遇した時の対処法をお伝えします。正しい知識を身に付けて、しっかり身を守りましょう。
Contents
スズメバチの生態【基本情報】

最初に、スズメバチの基本情報を見ていきましょう。
- 種類
- 生息地
- 食性
- 天敵
- 巣の見た目
上記のジャンルごとに解説していきます。
種類
日本には、スズメバチ属・クロスズメバチ属・ホオナガスズメバチ属の3属17種が知られており、一般的に「スズメバチ」と聞いて思い浮かぶのは主にスズメバチ属の8種です。その代表格には、以下のような種類があります。
- 最大級で攻撃性と毒性の高いオオスズメバチ
- 都市部に多く刺傷事故が報告されるキイロスズメバチ
- 比較的小型のコガタスズメバチ
属や種によって習性や巣の作り場所に違いがあるので、特徴を押さえておけば見分けがつくでしょう。
日本に生息するスズメバチの種類は、以下記事で詳しく解説しています。
生息地
スズメバチは、種類によって営巣場所が異なります。オオスズメバチは、地中や樹洞などに巣を作り、キイロスズメバチは、屋根裏や軒下に生息する傾向があります。
コガタスズメバチやホオナガスズメバチ属は、庭木や生け垣など人家近くの樹木付近に巣を設けるケースが多いので、庭作業時などには注意が必要。
それぞれの種類によって、市街地、郊外、山間地など環境に適応した場所を選んで生活しているのです。
食性
スズメバチは、樹液や果汁なども吸引しますが、主食は昆虫。成虫は、セミや蛾、バッタなどの昆虫を狩り、幼虫に持ち帰って成長を助けます。その代わり、成虫は幼虫から分泌される甘い液を栄養源にするという、独自の共生関係を築いているのが特徴。昆虫類の天敵として自然のバランス維持にも寄与していると言えるでしょう。
とは言え、オオスズメバチは同族のミツバチを襲うので、養蜂家にとって脅威的な存在です。
天敵
昆虫を食べるスズメバチですが、天敵もまた昆虫です。大型トンボのオニヤンマは、俊敏な飛行力でスズメバチを捕食します。クモに巣を張られて捕獲された例もあるほど。
その他、猛禽類のモズやハチクマもスズメバチを狩る天敵です。クマが巣を丸ごと食べたり、野生のニワトリがスズメバチを捕食する場合もあります。
スズメバチの天敵は、以下の記事で詳しく解説しています。
巣の見た目
スズメバチの巣は、外皮に包まれた白茶色のマーブル模様が特徴的です。春先の女王バチが単独で巣を作る時期には、10cm程度の徳利やフラスコ型ですが、夏〜秋になると球形へと成長し、直径30〜60cmまで大きくなるケースもあります。
表面は波打つような模様があり、巣穴は原則一つ。一方、アシナガバチの巣はシャワーヘッド型で、六角形の巣室がむき出しなので対照的と言えるでしょう。また、ミツバチの巣は平たい板状で、蜜蝋製の黄色がかった色調。
スズメバチの巣は、堅固で厚い外殻があり、初期こそ見つけにくいものの、成長すると一目で識別できるほどの存在感になります。
他のハチの巣との見分け方は、以下の記事を参考にしてください。
スズメバチの生態【攻撃時】

次に、攻撃する時のスズメバチの生態をご紹介します。
- 護身のために攻撃する
- 段階を踏んでから攻撃する
- 警報フェロモンを出す
危険回避のためにも、チェックしていきましょう。
護身のために攻撃する
スズメバチは、自分や巣が危険にさらされると防衛本能で攻撃してきます。無意味に人を襲うわけではなく、自衛のための反応なのです。
巣や幼虫を守ろうとする本能から、特に、幼虫の成長期である夏〜秋は警戒心が強く、ほんの少し近づくだけでも咄嗟の行動で攻撃しかねません。スズメバチの視点に立てば、私たちが近づく行為そのものが「敵」というわけです。
段階を踏んでから攻撃する
スズメバチは、段階的な威嚇行動で警告アピールしてから攻撃態勢を取ります。まず空中で観察しつつ警戒し始め、その後、大あごをカチカチ鳴らしながら周囲を飛ぶ威嚇フェーズに進み、それでも敵と見なした対象が去らない場合は、その段階で攻撃を仕掛けます。
攻撃的なイメージばかりが先行していますが、むやみやたらに毒針を向けるのではなく、相手にも退避の機会を与えているわけです。
つまり、警戒や威嚇に気付いた時点ですぐに退避すれば、攻撃される恐れは大幅に下がる点を覚えておきましょう。
スズメバチの威嚇音については、以下記事で詳しく解説しています。
警報フェロモンを出す
攻撃の合図として知っておくべき点として、スズメバチの「警報フェロモン」が挙げられます。
スズメバチが針から毒液と共に放出する化学物質は「警報フェロモン」と呼ばれ、仲間に危険を知らせる信号として機能します。
毒針で刺した最初の一匹が発する警報フェロモンを、群れ全体が嗅ぎ取り興奮すると、一斉攻撃に打って出るため大変危険。
とにかく刺激を与えず、早い段階でその場を去りましょう。
スズメバチの生態【時期・時間】

スズメバチが活動する時期や時間などの習性についても、解説していきます。
- 夏から秋が活動期
- 早朝に活動
- 雨や寒い時期は活動が控えめ
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
夏から秋が活動期
スズメバチは、一般的に4月〜11月に活動します。特に、6月下旬から10月頃が盛期とされていて、子育てが活発な夏から初秋(7〜9月)は、個体数も増えて活動も活発になるので、刺される事故が多発する時期と言えるでしょう。
新女王が誕生する秋には、巣の数が減少傾向になりますが、11月頃までは働きバチが生存するため注意が必要です。
詳しい活動時期は、以下の記事を参考にしてください。
早朝に活動
スズメバチの活動を時間別にも見ていきましょう。
スズメバチは、朝日が昇るとともに活動を開始し、午前6〜7時が最も活発な時間帯です。日中は、餌採取や巣材回収、幼虫への給餌などで忙しく飛び回り、夕方にかけて徐々に巣へ戻ります。
夜間は、視力が低下するためほとんど活動しません。この生態を踏まえると、早朝や巣に戻る夕方は、集団に遭遇するリスクが高い時間帯といえます。
雨や寒い時期は活動が控えめ
スズメバチは、寒さや雨に弱いので、気温が15℃以下になると活動が鈍ります。さらに、10℃以下ではほとんど動けなくなります。
また、羽が濡れる雨の日も飛行効率が落ちるため、活動がかなり少ない傾向にあります。
それぞれの習性を総合的に見ると、春先や秋口の涼しい日、雨の日などは刺されるリスクが低くなるので、巣の駆除や点検を検討するタイミングとして適していると言えるでしょう。
スズメバチの生態【巣】

最後の特徴として、スズメバチの巣に触れていきます。
- 巣は女王バチのみで作る
- 常に見張り役がいる
- 毎年新しく巣を作る
巣一つとっても、スズメバチは独特ですよ。
巣は女王バチのみで作る
スズメバチの巣は、春(4月〜6月)に、冬を越した女王バチが一匹で作り始めます。まず、小さなフラスコ型の巣を構築してから、卵を産んで幼虫を育てます。幼虫が羽化すると、働きバチが巣作りを引き継ぎます。
この段階では巣がまだ小さく、女王バチの警戒能力も比較的低いため、初期の駆除は比較的ローリスクで対処できるでしょう。
しかし、成長すると大きく頑丈になり、完全駆除には専門業者でも注意が必要です。
スズメバチの女王バチについては、以下記事で特徴を解説しています。
常に見張り役がいる
完成したスズメバチの巣には、「見張りバチ」と呼ばれる働きバチが常時待機し、巣の入口や周辺を巡回して外敵を監視しています。
見張り役だけあって、視界に入った人や物にすぐ気付き、飛行や威嚇行動で警告したのち、最初に攻撃を仕掛けるのも見張りバチ。見張りバチが警報フェロモンを出すと、仲間が一斉に集まるため、1匹だからと言ってあなどってはいけません。
毎年新しく巣を作る
スズメバチは、毎年新しく巣を作ります。働きバチは秋に死に、女王バチは次の年に一から新しく作るため、一度使用した巣は使い回しません。
冬になると中身は空の状態で放置されたままで、再度使われるわけではありませんが、結局翌年も、新たな女王バチが同じ場所に営巣するケースが多いのが気を付けるべき点。活動時期を過ごせる安全な場所だと認識するため、毎年同じ軒下や木の陰を狙う性質があるのです。
スズメバチを見かけた時の対処法

スズメバチの生態をご紹介しましたが、実際に見かけた時の対処法もご紹介しましょう。
- 騒いだり動いたりしない
- 黒っぽい服装は避ける
- 虫よけスプレーは使わない
- 巣を見つけたらすぐに駆除する
それぞれ参考にしてください。
騒いだり動いたりしない
スズメバチは、刺激を与えると敵と見なし、敵に向かって攻撃してきます。スズメバチを刺激するような大声や大きな動作などの急な動きはやめましょう。
ハチが近くに飛んで来たら、思わず手で払ったり悲鳴をあげたりしてしまいがちですが、それは一番のNG行動。近くに飛んでいる状態は、まだ警告の段階なので、できるだけ慌てず、ゆっくりその場から距離を取れば、攻撃段階に進む確率を大幅に減らせます。
子どもやペットがいる場合は、落ち着くように声がけすると良いでしょう。
黒っぽい服装は避ける
スズメバチは、暗い色や強いコントラストに敏感に反応し、攻撃対象と誤認しやすい傾向があります。
そのため、屋外での作業や庭掃除の際は、白やベージュなどの明るい色を選ぶと安心。また、香水や花の香りもハチを誘い寄せやすいため、黒っぽく人工的な香りのする装いは避けてください。
虫よけスプレーは使わない
一般的な虫よけスプレーだけでなく、ハチ専用の防虫スプレーでも、スズメバチには効果が薄いのが実状です。ハチの中でもスズメバチは特に頑丈なので、即効性を謳うハチ駆除スプレーですら「スズメバチは例外」と記載されている製品が多く見られます。
むやみに虫よけスプレーを散布すると、その行為自体が刺激になって攻撃されかねません。
巣を見つけたらすぐに駆除する
スズメバチの巣を発見したら、とにかく速やかに専門業者に相談しましょう。
巣を放置するとどんどん大きく拡大し、見張りバチや働きバチも増えていきます。警戒が強まり、刺されるリスクが増加するので、夜間や早朝などハチの活動が少ない時間帯に、駆除してもらうと良いでしょう。
特に、高所や天井裏などの難所や、アレルギーがある方がいる場合は、迷わず専門家に依頼してください。
「ハチ駆除専門クリーンライフ」にお気軽にご相談ください!
スズメバチの刺された時の応急処置法

最後に、スズメバチに刺された時の応急処置法をご紹介します。
- まずその場から離れる
- 水で良く洗い流す
- 病院で診察してもらう
重要なポイントなので、いざという時のためにしっかりチェックしてください。
まずその場から離れる
スズメバチに刺されたら、まずは安全な場所へ静かに移動してください。巣や他のハチが近くにいる可能性が高く、刺激を受けると集団で襲われかねません。
ポイントは、大声や急な動きを避け、ゆっくりとその場を離れること。最低でも50メートル以上、安全圏まで距離を取りましょう。焦らずに離れれば、警戒フェロモンをかぎつけた他の蜂たちに集団で襲われる二次被害が防げます。
水で良く洗い流す
刺された直後は、患部に付いた毒液や汚れを水で丁寧に洗い流してください。ハチの毒は水溶性なので、流水ですすげば、毒素の広がりを抑えられます。
また、冷水で洗い流すと、患部の血管が収縮して毒の吸収を遅らせられる点も重要ポイント。水道水でも問題ないので、即対処するようにしてください。
病院で診察してもらう
応急処置をした後も、すべき対応は続きます。
スズメバチに刺されると、局所的な痛み・腫れにとどまらず、めまいや吐き気などのアナフィラキシーショックが出る場合があります。
異常が見られたら、速やかに医療機関へ行きましょう。皮膚炎科や救急科で診察を受け、必要であればステロイド軟膏や抗ヒスタミン薬を投入してください。
過去に刺された経験がある人は、重症化しやすいため、特にすばやい対応が必須です。
スズメバチの生態を知って身を守ろう!
スズメバチの生態について、詳しく解説しました。
いざと言う時に安全を保てるように、スズメバチがどのような時に活動的、かつ攻撃的になるのか、知識として身に付けておきましょう。
そして、もしスズメバチに遭遇したら、焦らずプロの専門業者に駆除を依頼してください。
『ハチ駆除専門クリーンライフ』は、スズメバチをはじめとする蜂駆除実績が豊富。安全性の確保や再発防止など、安心してお任せできる体制が整っている専門業者です。
年中無休で最短即日対応も可能なので、ぜひお気軽にご相談ください。
「ハチ駆除専門クリーンライフ」にお気軽にご相談ください!
スズメバチの生態に関するよくある質問
- 巣はどこに作られやすいですか?
- スズメバチは、雨風をしのげて人の出入りが少ない場所を好んで巣を作ります。典型的な場所として、軒下や屋根裏、木のうろ、床下、換気口などが挙げられます。
また、過去に巣を作った場所は、安全だと認識して再び営巣する傾向があるので、十分注意してください。
- スズメバチはどのくらいの距離で反応しますか?
- 種類によって異なりますが、一般的に巣の半径2〜5メートル以内に入ると警戒態勢に入るでしょう。
見張り役のハチが巣のまわりを常に監視していて、侵入者を確認すると警告飛行や威嚇音を発します。威嚇段階でも敵が退かないと、満を持して攻撃を仕掛けてくるのです。
- 巣には何匹くらいのハチがいるのですか?
- スズメバチの巣は大きく、秋の最盛期にはキイロスズメバチで数千匹、オオスズメバチで数百匹規模になります。
それだけの数のハチが、巣を守るために一斉に攻撃してくるのを想像すると、危険度が非常に高いのは想像にたやすいですね。
- 同じ場所に何度も巣を作られるのはなぜですか?
- スズメバチは、営巣場所を記憶する性質があります。巣自体の再利用はしないものの、巣が前シーズンを通して営みを続けられたのは、その場所が安全だった証拠とだと認識して、翌年の新女王が同じ場所を選ぶケースが多いのです。
- どのようなケースでスズメバチ駆除業者に相談すべきですか?
- 巣を見つけた時点で駆除業者に依頼すべきです。
特に、巣が大きい、複数ある、高所にあるなどのケースでは、専門の防護装備と知識がないと対処が難しいので、安全確保のためにも、早めに専門業者へ相談しましょう。
危険ですので、無理せず
まずはプロに相談を!
- お支払い方法
-
- 現金払い

- 各種クレジットカード対応

- コンビニ後払い

- 銀行振込

- QR決済